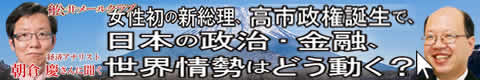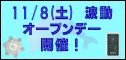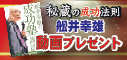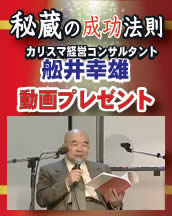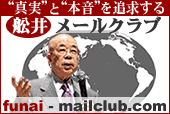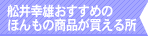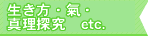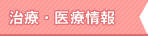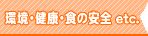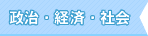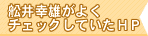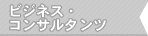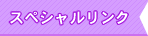トップが語る、「いま、伝えたいこと」
先日、一般社団法人ATAMIミライ共創機構が主催する「アタミラ miniマルシェ」に行ってきました。さすが、理事メンバー4名が皆、女性であることも手伝ってか、細やかな工夫と配慮満載のイベントで、満喫して帰ってきました。
地元の魚屋さんである「宇田水産」さんの未活用魚を七輪で焼いたものや、ジビエ解体施設「matseline 山ししや」さんの鹿肉の串焼きなど、ユニークなお料理も提供されていました。いろんな意味で、「環境問題」について考えさせられるイベントであったとも言えます。
海の印象が強い熱海ですが、実は原生林が息づく豊かな山と美味しい柑橘があります。その山で育った鹿や猪を、害獣ではなく「山の恵」としていただく……。そんな想いから、柑橘の街、熱海から「橘鹿(きっか)」と「橘猪(きっちょ)」と名付け、プロデュースされているのが、山ししやの高志織さんです。とにかく、柔らかくて、においもなく、美味しい!!ジビエの印象変わりました……。
あたみ・パンダの森ほいくえんで毎年行っているのが、「焼き芋&餅つき大会」ですが、今年は、小さなお芋畑が台湾リスに荒らされて不作……。どうしようかなって思っていたら、思わぬ救世主が……。「山の高橋農園」という伊豆の国のポツンと農家で育ったお野菜が出展されていたのです。1945年から疎開されていて、拓いた山の上の畑にて、もう4代繋いでこられました。一家とヤギとネコで、年間80〜90種類ほどの野菜とお茶、米麦大豆を育てています。そこで、なんと栽培期間中、無農薬&無化学肥料で育てたさつまいもを大量にゲット(当日はご迷惑をかけるので、別途注文しました)。救われました!
そして、フリマでは、なんと31インチのウォッシュドのリーバイスをゲット!裾にスリットが入った珍しいもので、なんと700円!これは、よいお買い物をしました。いっぱいあったお洋服があっという間に少なくなってしまうほど人気でした。大量生産、大量消費社会で、いまあらためて「リユース」は大きく注目を集めています。近年、リユースショップの出店が増えていますが、古いものへのノスタルジーやオシャレさを求めるという意味だけではなく、やはり、環境負荷軽減への注目も高まっているのではないかと想像します。
そこで、今回は、洋服のリサイクルについて、考えてみたいと思いました。
日本の繊維リサイクル率は約30%にとどまり、年間50万トンを超える衣類が焼却や埋め立てによって処分されています。この背景には、ファストファッションの普及による衣服の短命化、混紡素材が増えてリサイクルが難しくなったこと、自治体間で回収ルールが統一されていないことなど、複数の要因が複雑に絡み合っています。衣類は本来、ぼくたちの生活を彩る身近な存在ですが、その役目を終えた後の行き先は、思っている以上に環境負荷の大きい問題となっています。では現在のどこに課題があり、未来に向けてどのような取り組みが求められるのでしょうか。
まず、リサイクルの現状を見てみると、技術とコストの問題が大きな壁となっています。現代の衣類の多くは複数素材を組み合わせた混紡繊維で作られており、これを再び素材ごとに分離する技術は十分に確立していません。加えて、ボタンやファスナーなどの付属品が分別をさらに難しくしています。仮に分離できたとしても、マテリアルリサイクルでは繊維が短くなって品質が落ち、ケミカルリサイクルは高品質を保てるものの設備投資が非常に大きくなります。しかも、リサイクルには大きな環境負荷がかかるのです。結果として、新品のバージン素材の方が安価で扱いやすいため、市場ではそちらが優先され、リサイクルの普及が進みにくい状況が続いています。リサイクルを本格的に広げるためには、技術革新とコストの両面で大きなブレークスルーが必要だと言えます。
一方で、リサイクルより環境負荷が低いとされるのがリユースです。服をそのままの形で次の人に使ってもらうリユースは、追加のエネルギーがほとんど必要なく、環境への効果が非常に大きい方法です。フリマアプリや古着店の普及により、以前よりも気軽にリユースに参加できる環境が整ってきました。しかし、リユースにも限界があります。低品質な衣服は市場で求められにくく、海外へ輸出された後に現地で廃棄されてしまうケースもあります。また、汚れや破れがあると受け入れ先が限られるため、日頃から衣類を丁寧に扱う意識が不可欠です。リユースは確かに環境に優しい選択ですが、その効果を十分に発揮するには、消費者の「選び方」と「使い方」も問われる方法であることが分かります。
近年注目されているアップサイクルは、古着や廃棄される衣類を新しい価値ある製品へと再生する取り組みです。デザイナーによる一点もののリメイクや、不要な生地を活用した雑貨づくりなど、創造性の高さとストーリー性が魅力で、消費者の共感を得やすい特徴があります。アップサイクル商品には「本来捨てられるはずだった素材を救う」という物語が宿り、ブランド価値を高め、文化としての広がりにもつながります。しかし、大きな課題である大量廃棄を一気に解決できるほどの生産量にはなりにくく、職人性やデザイン性に依存するため大量生産には向きません。つまり、アップサイクルは意識改革や価値創造に大きく貢献するものの、廃棄量の削減という面では補完的な役割を担う方法と言えます。
このように、リサイクル・リユース・アップサイクルのそれぞれには利点と短所がありますが、どれが正解という話ではありません。それぞれが持つ役割を理解し、社会全体で最適な組み合わせを作っていくことが重要です。特に、衣類の環境負荷の多くが生産段階に集中しているという点を踏まえると、消費者としてのぼくたちができる最も効果的な行動は「買う量を減らし、長く着る」という非常にシンプルな行動です。長持ちする素材や縫製のしっかりした服を選び、洗濯や保管を丁寧に行い、必要のない衝動買いを避けるという小さな行動が、結果として大量生産・大量廃棄のサイクルを緩めていきます。循環型社会の実現は、消費者自身の意識によって大きく左右されるのです。
また、衣類を手放す際の行動も未来を大きく変えます。まだ着られる服はリユースに、着られない服は企業の回収プログラムや自治体の古布回収へ出すことで、資源が循環へと戻っていきます。日本では自治体によって回収ルールが異なり分かりづらいという課題がありますが、今後は全国的な基準づくりや、ごみ分別アプリなどのデジタル支援が普及することで、消費者が迷わず適切な手放し方を選べる社会へと変わっていく可能性があります。というか、そうしていかねばなりません。こうした仕組みが整えば、現在焼却されている膨大な量の衣類の「出口」を確実に変えることができます。
生産する企業にも重要な責任があります。単一素材で作られた衣類や、付属品を取り外しやすいデザインはリサイクルを容易にし、サプライチェーン全体の環境負荷を下げます。さらに、ヨーロッパで進んでいる売れ残り衣料品の廃棄禁止や、生産者が廃棄まで責任を持つEPR(拡大生産者責任)の仕組みが日本でも導入されれば、衣類循環の基盤づくりは大きく前進するはずです。企業、自治体、消費者が「リサイクルしやすい服」「長く着られる服」「循環が前提の服」という価値観を共有することで、はじめて社会全体の方向性が一致していきます。
最終的に未来をつくるのは、ぼくたち一人ひとりの選択です。服をどう買い、どう使い、どう手放すかという日々の行動が、繊維リサイクル率30%という現状を確実に変えていきます。ファッションは流行を追うだけのものではなく、ぼくたちの価値観そのものを映し出す存在です。だからこそ、サステナブルな選択をすることは、自分自身の生き方をより豊かにする選択でもあります。明日手に取る一着を選ぶとき、少しだけ視点を変えることで、その行動は未来への小さな投資になります。衣類の循環は、制度や技術の進化だけでなく、ぼくたちがどのような物語を紡いでいくかによって形づくられていくのだと思います。
2025.11.17:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】神さまライフ (※舩井勝仁執筆)
2025.11.10:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】「ひすいこたろうさんに学ぶ、やわらかく生きるということ」―「幸せにならなくたっていいんだよ」と言われた日のこと― (※佐野浩一執筆)
2025.11.03:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】サムシンググレートの聖書 (※舩井勝仁執筆)
舩井 勝仁 (ふない かつひと)
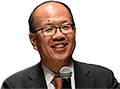 株式会社船井本社 代表取締役社長 株式会社船井本社 代表取締役社長1964年大阪府生まれ。1988年(株)船井総合研究所入社。1998年同社常務取締役 同社の金融部門やIT部門の子会社である船井キャピタル(株)、(株)船井情報システムズの代表取締役に就任し、コンサルティングの周辺分野の開拓に努める。 2008年「競争や策略やだましあいのない新しい社会を築く」という父・舩井幸雄の思いに共鳴し、(株)船井本社の社長に就任。「有意の人」の集合意識で「ミロクの世」を創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動を続けた。(※「にんげんクラブ」の活動は2024年3月末に終了) 著書に『生き方の原理を変えよう』 |
佐野 浩一(さの こういち) 株式会社本物研究所 代表取締役会長 株式会社本物研究所 代表取締役会長公益財団法人舩井幸雄記念館 代表理事 ライフカラーカウンセラー認定協会 代表 1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。 著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』 |