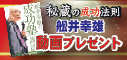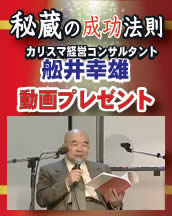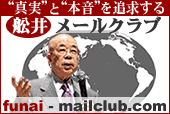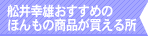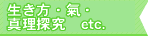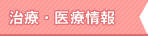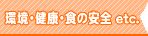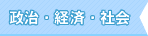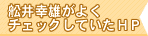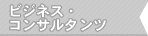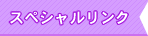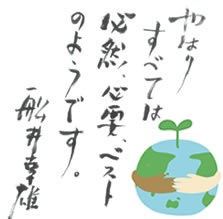
トップが語る、「いま、伝えたいこと」
私はよく本を読む方だと思います。
送られてくる本も毎日何冊かありますし、自分でもよく本を買いますから、いつも机の上には読みたい本が10冊以上は積まれています。
最近読んだ本で著者が私と親しい人の本は、
・ペマ・ギャルポ著『北京五輪後のバブル崩壊』(08年7月8日 あ・うん刊)。
・ベンジャミン・フルフォード著『中国が目論む世界支配の正体』(08年7月30日 扶桑社刊)
・加治将一著『舞い降りた天皇』(上・下)(08年8月1日 詳伝社刊)
・副島隆彦著『時代を見通す力』(08年8月7日 PHP研究所刊)
などですが、やはりそれぞれが参考になります。
とはいえ、どの本も著者の特性を知り、客観的に読む必要があります。
そのためには「まえがき」と「あとがき」を充分読むのがもっとも大事だ…というのが私の意見です。その本の中でもっとも大事なことが、そこには集約されて書かれているのがふつうで、客観的判断の助けになります。
たとえば前述のフルフォードさんの本のあとがきの、その一部を紹介しますと、つぎのように書かれています。
彼の経歴を知って読むと、彼が何を言いたいか、これだけでよく分ります。
「米中対決」の趨勢はいま、中国の勝利に大きく傾きつつある――。
私は本書の結論として、敢えてこう宣言しておきたい。その確信を強めたのは、香港とマカオの取材を通じてのことだった。
いまではもう忘れられているが、香港返還直前、中国による「1国2制度」への挑戦を楽観視する向きはごく少数だった。マカオについても同様で、低迷していた「カジノ依存症」経済の建て直しは、至難の業とされていたのだ。
しかし本書で見てきたとおり、中国は欧米資本とのマネー戦争で「香港」防衛に成功。マカオでは、「カネでカネを生む」ことを究極の目的とする資本主義の申し子、ラスベガスのギャンブル資本を飼いならしている。
中国は、旧列強宗主国の下で成長の「限界」に直面していた両地域に、新たな未来を切りひらいて見せたのだ。世界市場において、どの国がこのような形での「領土奪還」を成し遂げただろうか。このまま台湾をも取り戻せば、中国は列強に蹂躙され、恥辱にまみれた「失われた100年」を完全に克服することになる。「眠れる獅子」は覚醒までに1世紀の時間を費やし、いままさに立ち上がるのだ。
しかし問題は、そうした中国の復活が、われわれの世界にとって利益になるかどうかだ。来るべき「パクス・チャイナ」が、前時代の支配者と同様に暴力と権威をもって覇権を維持しようとするなら、それは私たちにとって「新しい未来」と呼ぶ価値のないものになってしまう(転載ここまで)。
ともかく、本や情報、ニュースは客観的に把握するコツをおぼえましょう。
本の「まえがき」「あとがき」を吟味するのもそのコツです。
=以上=
2008.08.25:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】新しい本を書きはじめました
2008.08.22:【先週のびっくりより】気になって仕方のない「この世の仕組み」
2008.08.18:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】あの世のひみつ
2008.08.15:【先週のびっくりより】携帯電話などが出す超低周波には注意が必要
2008.08.11:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】老荘思想
2008.08.08:【先週のびっくりより】月刊『にんげんクラブ』変身の効果と人気
2008.08.04:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】客観的に掴むコツ
2008.08.01:【先週のびっくりより】1日に19時間働き、37年間で家にいた(休んだ)のは10日間もない男
ライフカラーカウンセラー認定協会 代表
1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。
著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』