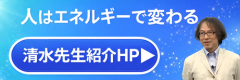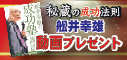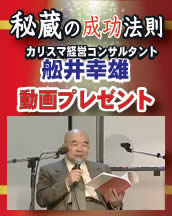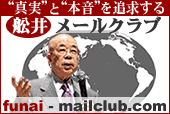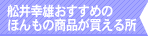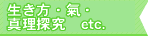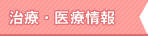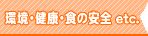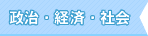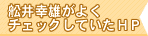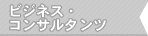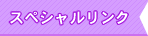トップが語る、「いま、伝えたいこと」
ある頃から、哲学の「哲」という字がとても好きになりました。
振り返ってみると、高校時代に習った「倫理社会」の先生のご専門が哲学であったこともあり、憧れの分野でもありました。物事を真剣に考えること、物事を本質からとらえて結論を導くことなどの大事さをその先生から学ばせてもらったように思います。
もしかすると、そんな影響もあったのかもしれません。
「哲学」はいまなお一種の憧れの対象として、あるいは自己研鑽の課題としてとらえる自分がいます。
ときとして、人は迷ってしまいます。
判断のつかないことも結構あります。迷うことだってあります。とくに、いまのような混迷を極めた時代に生きていると、芯になる考え方、方針、理念が揺れてしまっては、余計に判断を狂わせてしまいます。
「哲学」を持つといっても、なかなかそのレベルまで達することはむずかしいように思えてしまいます。ただ、舩井幸雄が「舩井流」として伝えてきたことの多くは、「哲学」だったのだと、最近ストンと腑に落ちたのです。
たとえば、「よいことはやり、悪いことはやめる」という良心に則った判断はとてもシンプルかつ重要だと思います。そのときにその根幹をなすのが、自身の持つ良心のレベルです。人間的成長とともに、良心のレベルも上がってくるといいますから、そのとき、そのときは良心に照らして、自信を持ってジャッジしたいものだと思います。
また、「世のため、人のため」というマクロな考え方で生きる、あるいは経営することを生涯説き続けてきたのも、まさにそれこそが「哲学」の根幹をなすものだということにも気づきました。私自身は、まだそれを「自分の言葉」として語るには少し時間がかかりそうな気もしますが、これは、結構大きな課題です。私もしっかり考え、しっかりとした哲学を自身の中に育てていきたいと思っています。
さて、近年、「哲学コンサル」という領域が生まれているようです。ポジティブな倫理の探求として、さまざまなジレンマを踏まえて『善いこと』を導き出すためのアプローチだと説明されていました。
先ごろ、GoogleやAppleでフルタイムの「企業専属哲学者」が雇用されたことは、世界中を驚嘆させました。でも、実際には、これまでも哲学から経営や人間を見つめる「舩井流コンサルティング」が存在し、一方で、グローバル世界を牽引するような最大手企業では、哲学者が力を発揮し、貢献できる場面が数多く存在してきたようです。だからこそ、このニュースは、重要かつ意義のあることだと考えます。
いまの社会では、グローバル化が進む中、多種多様な価値観が交錯していることや、AIをはじめとする科学技術の進歩が、新たな倫理的問題を生み出していることは事実です。そのような中、これまで一般企業では、「データ分析」そのものが問題解決の手法のメインであると考えられてきたように思いますが、より一層分析できない「答えのない問い」が増えてきていることも事実です。それらを自力で解決しつつ、自社の「世界観」を伝えていくことが求められています。そこでは、もう数字やデータ、分析などが通用しない「哲学」での考察や洞察が必要となってくるのです。
グローバル化が進んだいま、たとえば多くの商品について、「作られる場所」と「消費される場所」の距離が開いていて、国をまたぐことも珍しくありません。そうすると、文化的な背景の違う人に向けて商品やサービスを開発するわけですから、技術だけではなく、使う人に思いを馳せる力もより一層求められるはずです。
近年、大手の化粧品会社で、既存の製品から『美白』などの表現を削除する動きが広まりました。美白には、人種差別的なバイアスが潜在的に含まれるからです。当たり前のように受け入れられていた前提を疑って、『何がほんとうに善いことなのか』を追究し、製品や企業活動に反映させていくことは、積極的な倫理の探求といってよいと思います。とくに、本質的な「多様性」を丁寧に認めていこうとすると、必須マターとなることは当然です。
企業活動において売り上げ・利益と倫理とのジレンマに直面したり、従来の常識に流されたりしてしまうことは、多々あることです。そうしたとき『自分たちは何を善とするのか』を深掘りして言語化する必要が増してきていることを実感します。
まさに、舩井幸雄が示してきた「勇気」=「よいと思うことはやり、よくないことはやめよう」というシンプルな経営哲学そのものが、いま注目されてきているということなのです。
一方、『自社の世界観を明らかにする』ことは、相対的な善悪を超えた理念構築の支援です。例えば、AIや遺伝子治療などの新興技術は、研究・開発・実装の場面において、まだ法制度が追いついていない領域です。面白いのは、アメリカでは、法律が善しあしを決めてないところに踏み込んで新しい価値を提案し、自分たちで原則を作ろうとする姿勢があります。その根幹では自由を重んじる精神が底流に流れています。では、ヨーロッパはどうかというと、予見的に悲劇についてを避けて研究開発やイノベーションを進めていこうとする傾向があるという見方があると知りました。それは人権や責任を根幹に置いているからだと思います。日本の企業活動においても、自社の根幹にどんな根源的価値を据えるのか、追究する必要性が出てきていると考えます。
感染症のパンデミックやDXによって、企業に迫られるビジネスの進化。さらに社会的責任としてSDGsの取り組みにも着手していかなくてはなりません。劇的に変わり行く世界、企業がどのようなビジョンやパーパスを掲げるべきかを考えることについても、こうした倫理や世界観をどうとらえていくかの重要性は高まってきているように感じてなりません。
さて、「哲学コンサルティング」に話を戻すと、それは、「哲学の知識や思考法、態度、対話を通じて、企業の課題あるいは社会課題について分析したり、解決に向けて探求したりすること」だと定義されるようです。
たとえば、「働き方改革」の一環で、働きやすい職場や女性活躍を実現しようと、何かしらの施策を講じるとします。しかし、個人個人で働きやすい職場や女性活躍の定義は異なりますし、世代ごとの価値観も異なります。他社や他業種の好事例が、自社に当てはまるとは限らないので悩ましいのです。だからこそ、自社のビジョンやパーパスに則って、思索を深め、「どうあるべきか?」を引き出してくる営みが必要なのだと思います。そうした点で、それをうまく引き出してくれる支援を求める動きが増えてきているのだと思います。
最近、企業の中には、あらためてビジョンやパーパスを見直し、社会的な存在意義を再定義しようとする向きがあるようです。あるいはSDGsやESGにどう向き合い、コミットしていくのかを模索している企業もあるということです。
そのときに重要な役割を果たすのは、経営者の価値観であり、それに共鳴する、そこで働く人々の存在です。不透明で不確実な時代を生き抜く原動力となる価値観をつかむことが、いまさらに求められ、そのために役立つ手法が、哲学コンサルティングだといえそうです。
ただ、哲学こそ、自身で深めるもの、考えに考えて、「自分は何者か?」「自社は何のために存在するのか?」にたどりつくものとも言えます。
舩井幸雄をご存じで、学んでこられた皆さんとともに、あらためて「舩井流経営法」「舩井流人間学」=「舩井流哲学」をいま一度、こうした視点で丁寧に反芻し、再発見していく営みを愉しみたいと思っています。
感謝
2022.04.18:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】哲学と経営 (※佐野浩一執筆)
2022.04.11:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】北海道の重要性 (※舩井勝仁執筆)
2022.04.04:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】学び直しの時代、仕事を趣味にできるか? (※佐野浩一執筆)
舩井 勝仁 (ふない かつひと)
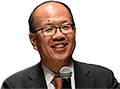 株式会社船井本社 代表取締役社長 株式会社船井本社 代表取締役社長1964年大阪府生まれ。1988年(株)船井総合研究所入社。1998年同社常務取締役 同社の金融部門やIT部門の子会社である船井キャピタル(株)、(株)船井情報システムズの代表取締役に就任し、コンサルティングの周辺分野の開拓に努める。 2008年「競争や策略やだましあいのない新しい社会を築く」という父・舩井幸雄の思いに共鳴し、(株)船井本社の社長に就任。「有意の人」の集合意識で「ミロクの世」を創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動を続けた。(※「にんげんクラブ」の活動は2024年3月末に終了) 著書に『生き方の原理を変えよう』 |
佐野 浩一(さの こういち) 株式会社本物研究所 代表取締役会長 株式会社本物研究所 代表取締役会長公益財団法人舩井幸雄記念館 代表理事 ライフカラーカウンセラー認定協会 代表 1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。 著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』 |