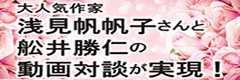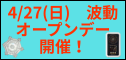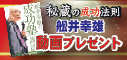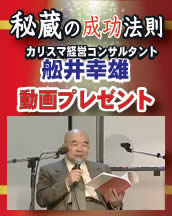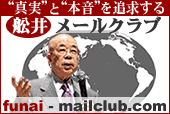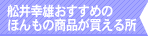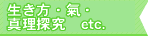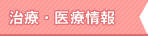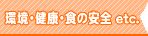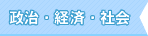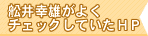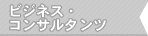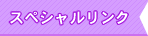トップが語る、「いま、伝えたいこと」
トランプ大統領は想像を超えた存在であり、破壊と創造を目指してとてもインパクトのある相互関税政策を発表しました。これによって、4月3日の1日だけで、日米欧の主要国の株式市場だけで500兆円の価値が喪失しましたが、トランプ氏にとっては想定内だったようにも思います。政策当局(通常は日銀やFRB等の中央銀行の場合が多い)と金融市場は一種のだまし合いのような駆け引きをしています。市場は当局の意向をなるべく早く読み込んで相場を形成していきます。当局側は、なるべく先読みされずにサプライズを起こした方が大きなインパクトを与えることができるので金融市場におけるアドバンテージを握ることがきます。そういう意味では、トランプ大統領が完全に勝利したと言えるのではないでしょうか。
思い出すのは、2013年4月と2014年10月に行われたいわゆる黒田バズーカ。アベノミクス政策の目玉になっていく金融政策でしたが、それまでの伝統的なやり方を根本的に変えるものでマーケットに与えた衝撃は非常に大きなものになりました。個人的には、2014年10月の第2弾の発表をちょうど父が亡くなった最初の大きなイベントであった「舩井SAKIGAKE☆フォーラム」の準備をしていたパシフィコ横浜の控室で知って、舩井幸雄がなくなったという衝撃を受け止めかねていた当時の自分に社会も大きく変わっていくということを認識させてくれた出来事になりました。
いまから考えればですが、船井本社のビジネスを父がいなければじり貧になるコンテンツビジネスから本格的に投資業に切り替えていくきっかけになりました。トランプ政権が各国に課すと言っている、驚くように高い相互関税は第2次世界大戦後にアメリカ中心に進めてきた自由貿易体制が終焉していくことの象徴で、トランプ大統領のやり方を受け入れるしかないのだと腹を括り、世の中の変化を冷静に読んで対処していく必要があるのだと思います。トランプ大統領は「MAGA(アメリカを再び偉大にする)」を実現するためには、何でもやるということが改めて明らかになったということを受け入れていくということです。
トランプ大統領がアメリカをダメにした元凶だと思っているのかもしれない金融界の大物である世界最大の投資運用会社ブラックロックのラリー・フィンクCEOは60/40戦略(株式60%、債券40%)は通用しなくなり、50/30/20戦略(株式50%、債券30%、プライベートエクイティ(ここでは、不動産や金や原油等の商品に代表される、株や債券以外の投資商品の意味だと思います)20%)のポートフォリオを作らなければいけないという発信を3月31日に投資家への手紙という形で公表しています。それぞれの立場で時代の変化にどう対応していくかを考えて行くことが大切です。
そんな環境下で今週紹介するのは、久保田進彦著『リキッド消費とは何か』(新潮新書)です。久保田先生はマーケティングを専門とする青山学院大学教授でマーケティング戦略を考える上で大きくトレンドを掴むということで本書を上梓されました。それをリキッド(液体:いままでは物を購入するという意味でソリッド(固体)だったと捉えて、その対比で液体消費と定義して(所有よりも体験、購入せずにシェアする、サブスク等)考察を進めていきます。
あらゆる意味でスピード化している社会、移動手段や伝達手段の高速化、スマートフォンの登場やAIの発達などの技術の発展により時代は大きく変わり、人々の消費行動にも大きな変化が見られるようになりました。それに合わせて思考の合理化が進み、以前よりも多くの人が実利を求めるようになり、若い世代ほどその傾向は顕著にみられ、我々の世代がそれについていくことができていない、そもそも理解する手前の段階で止まっているようにも感じる時代になってきました。
本書は若い世代に見られるリキッド消費(物を持たない消費の形)について解説する珍しいタイプの本であり、若者への理解の助けになってくれる一冊です。短命化、インスタント化のように言われる時代。趣味も一つのことに入れ込むよりも多種多様な選択肢の中から気分次第に、物も一つの物を大切にというより安い物をその時々合わせて買い換える。サブスクなどの多数の選択肢の中から自由に選ぶ事が可能なサービスが、当たり前となっています。それが正しい事かは個人の価値観に依存する問題ではありますが、それ自体が主流となっているのは間違いありません。
例えば車については、リキッド的消費を行なっている層は必要性が生じない限りは持たないという価値観を持っています。交通機関が発達した都市に住んでいる、独身であるなどの条件が重なれば実際所有しない選択肢は合理的であり、カーシェアリングや格安レンタカーは全国どこにでもあり、必要とあれば借りれば済む話、彼らにとってはむしろその状況で持つ方が理解に苦しむ、というのは容易に想像できます。この行動自体には若い世代は経済的に困窮しているという背景も考えられますが、実際冷静に考えてみるとその方が経済的には正しいパターンが大半です。その為か、リキッド消費的な行動は若い年代だけではなく、その上の世代にも少しずつ広がっているようです。
社会全体もそれに沿った流れを形成し、従来の消費スタイルを取る生き方ではやや不便を感じる時代になってきました。しかし完全に合わせるのは価値観や習慣の意味からもなかなか難しいように感じます。本書には事細かにリキッド消費の分析や様式が載っています。この中から自分にありそうな方法を選んで取り入れてみる、抵抗があっても思い切って触れてみる、そうすれば新しい発見や、若者への理解が進む良いきっかけになるかもしれません。こんなことを考えながらトランプ大統領が明確にしてくれつつある、時代にどう対処するかを考えて行く、ひとつの要素をしていきたいと思っています。
=以上=
2025.04.07:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】リキッド消費について考える (※舩井勝仁執筆)
舩井 勝仁 (ふない かつひと)
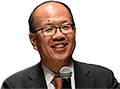 株式会社船井本社 代表取締役社長 株式会社船井本社 代表取締役社長1964年大阪府生まれ。1988年(株)船井総合研究所入社。1998年同社常務取締役 同社の金融部門やIT部門の子会社である船井キャピタル(株)、(株)船井情報システムズの代表取締役に就任し、コンサルティングの周辺分野の開拓に努める。 2008年「競争や策略やだましあいのない新しい社会を築く」という父・舩井幸雄の思いに共鳴し、(株)船井本社の社長に就任。「有意の人」の集合意識で「ミロクの世」を創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動を続けた。(※「にんげんクラブ」の活動は2024年3月末に終了) 著書に『生き方の原理を変えよう』 |
佐野 浩一(さの こういち) 株式会社本物研究所 代表取締役社長 株式会社本物研究所 代表取締役社長株式会社51コラボレーションズ 代表取締役会長 公益財団法人舩井幸雄記念館 代表理事 ライフカラーカウンセラー認定協会 代表 1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。 著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』 |