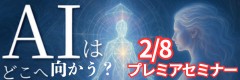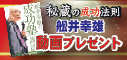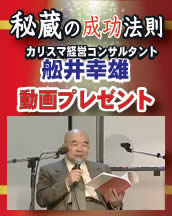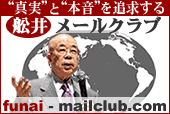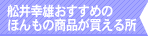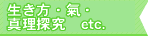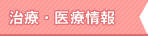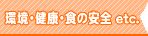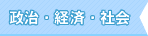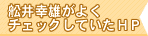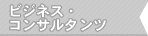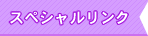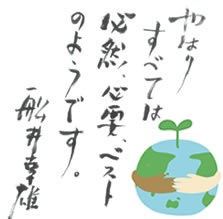
トップが語る、「いま、伝えたいこと」
私は、昭和30年代より、よく仕事で旅行し、多くの日本旅館に泊りました。
その中で、何回も訪れ、いつ行っても「ここが私にとってもっともぴたっとくるよい旅館だな」と思ったのが、由布院の「玉の湯」です。
「玉の湯」のオーナーは溝口薫平さん。私と同じ1933年(昭和8年)生まれで、現在、同社の代表取締役会長です。
先週の月曜日、私は午後1時から岐阜で講演をたのまれており、その後、名古屋での会合に参加するため、熱海発10:44分の新大阪行きの「ひかり」にのりました。私の座席は「8号車6D」でした。
ところが「8号車6C」に溝口薫平さんが座っていたのです。十余年ぶりの再会です。お互いにびっくりしました。しかも彼は奥さんやお嬢さんと一緒でした。静岡でこの日にある結婚式に参列するため、前夜は東京に泊って、今朝この電車にのったということで、熱海から静岡までの30分弱の時間、久しぶりにいろんなことを話しました。
彼は由布院という有名な温泉地を軌道にのせた人として有名です。そのことは拙著『まちはよみがえる』(2006年2月 ビジネス社刊)に詳述しています。同書の251〜253ページには以下のように書いていますが、これらには彼のアイディアが多く入っているのです。
●連泊しても旅館同士で料理がバッティングしない
こうした活動が実を結び、昭和50年代を迎えたころから、湯布院のブランドイメージは徐々に広がっていきます。
昭和56年には観光客が200万人の大台を超え、平成4年にはさらにその倍の400万人に達しました。その後のバブル崩壊で日本中の観光地が不況に沈む中、湯布院はいまも年間350万人〜400万人もの観光客を、安定的に維持しています。
「平成に入ると、私たちの目指した方向性は一気に開花しました。自然の風景に癒しを求める時代になり、不況の中で価格競争の果てに値崩れを起こした多くの温泉地が衰退する中、私たちは高いブランドを保つことができたのです」(溝口さん)
グレードの高いブランドイメージを保つために、湯布院の旅館はあえて大型化を避けています。観光客が増え、資金的な余裕ができてくると、街づくりメンバーの旅館も改装できるようになりましたが、それらはより高級化し、パイを小さくしてなかなか予約がとれない状態を、あえてつくり出しました。
また、農家と料理人によるネットワークを築いたのも、街づくりの具体的な方向性を示す一つの現れです。各旅館の調理人たち70〜80人で料理研究会をつくり、お互いのレシピを見せ合うことで、温泉街全体のグレードを上げました。そして農家とのネットワークにより、地産の新鮮な野菜を宿泊客にいつでも提供できる体制を整えています。
いま湯布院では、リピーターである「顧客」と「滞在型宿泊客」が増えました。
その際、町内で違う旅館に連泊しても、板前さん同士が情報交換していますから、料理がバッティングしないのです。こういう細やかな気遣いが「街全体でお客さんをお迎えする」という気持ちの現れなのです。
旅館組合では、それぞれの売上を情報公開しており、売上のうちその1万分の6を会費として供出するルールを設けています。これらはイベントの開催費用などにあてられます。また、どの旅館に泊まっても由布岳がきれいに見えるよう、建物には4階までの高さ制限を課す自主規制を設けるなど、協力して街を守ってきました。
「行政との距離のとり方も一つのコツです。街は私たちの方針によく賛成してくれましたし、他の都市に見られるような民間のやろうとすることに壁にならなかったのが幸いしました。それでも、民と官がお互いの役割分担を守り、私たちは行政に頼り過ぎず、官も私たちと一定の距離をとってきたことが、活動が長続きした要因でしょう」(溝口さん)
何もないことを誇りにしているので、音楽ホールも映画館もいまだにありません。毎年のイベントで場所を探すのに苦労しても、絶対に施設は造らない方針を貫いています。
いまでは湯布院は全国に知られ、多くの人が訪れるようになりました。しかし、ブランドイメージが定着したことで、街へのさまざまな進出もまた活発化します。バブル期になると、静かだった街にリゾート開発の波が押し寄せ、マンションや分譲別荘などの開発ラッシュが訪れたのです(転載ここまで)。
約30分間、彼とは「温泉地経営法」「これからの世界と日本」「いまの由布院盆地」「由布院温泉の特性」をはじめ、私と家内の友人の「小野孝寿枝さんのこと」などを話し、再会を約して静岡で分れました。
さわやかなうれしい30分でした。
ある意味では、彼は世界一の温泉旅館経営者であり、日本でも有数な地域活性化の達人だ・・・と、この間につくづく思いました。
久しぶりに会って、短時間でもまったく充実した時間をすごせる・・・これは驚きでしたが、ぜひ近い間に、久しぶりに家内とでもいっしょに「玉の湯」に行ってみたいと思っています。
(なお、「ゆふいん」には「由布院」ないし「湯布院」の両方の文字が使われています。)
=以上=
2007.06.25:【主な行動と主として感じたこと】船井幸雄の先週(2007年6月17日〜6月23日)の主な行動と主として感じたこと
2007.06.22:【先週のびっくりより】ストーンヒーリング
2007.06.20:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】競争は善ではない
2007.06.18:【主な行動と主として感じたこと】船井幸雄の先週(2007年6月10日〜6月16日)の主な行動と主として感じたこと
2007.06.15:【先週のびっくりより】びっくり・本物・感動セミナー参加者
2007.06.13:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】「肉食はいけない」と、こだわる必要はない
2007.06.11:【主な行動と主として感じたこと】船井幸雄の先週(2007年6月3日〜6月9日)の主な行動と主として感じたこと
2007.06.08:【先週のびっくりより】びっくりした一冊の本
2007.06.06:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】天と地が、今、私に語りを求めるところ
2007.06.04:【主な行動と主として感じたこと】船井幸雄の先週(2007年5月27日〜6月2日)の主な行動と主として感じたこと
2007.06.01:【先週のびっくりより】学者や役人のあり方
ライフカラーカウンセラー認定協会 代表
1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。
著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』