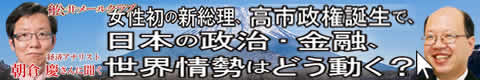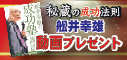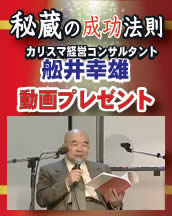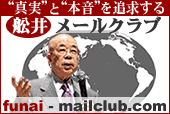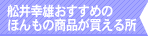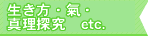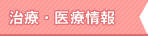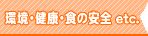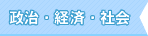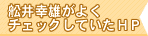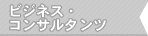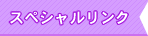ヤスのちょっとスピリチュアルな世界情勢予測
このページは、社会分析アナリストで著述家のヤス先生こと高島康司さんによるコラムページです。
アメリカ在住経験もあることから、アメリカ文化を知り、英語を自由に使いこなせるのが強みでもあるヤス先生は、世界中の情報を積極的に収集し、バランスのとれた分析、予測をされています。
スピリチュアルなことも上手く取り入れる柔軟な感性で、ヤス先生が混迷する今後の日本、そして世界の情勢を予測していきます。
日中関係が緊張している。これからどうなるのだろうか?
日中関係が安定する落としどころはあるのだろうか? まずは基本的な動きを確認しておこう。
現在の緊張の原因は、11月7日の衆院予算委員会でのやりとりだ。立憲民主党の議員が高市首相に対し、台湾をめぐってどのような状況が、日本にとって「存立危機事態」にあたるのかと質問した。
高市首相は、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と答えた。
「存立危機事態」とは、2015年成立の安全保障関連法に出てくる法的用語で、同盟国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす事態を指す。そうした状況では、脅威に対応するため、自衛隊が出動できる。
この高市首相の発言に、中国政府は激しく反発。中国外務省は「まったくひどい」と評した。中国の 薛剣・駐大阪総領事は8日にXで、高市首相の国会発言に関する報道記事を引用。「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」とコメントを書き加えた。
日本の木原官房長官は10日の記者会見で、薛氏の発言の趣旨は「明確ではない」ものの、「極めて不適切」だと述べた。
日本政府は薛氏の発言について中国側に抗議。中国政府も高市首相の発言について日本に抗議している。
高市首相は10日、発言の撤回を否定。「政府の従来の見解に沿ったもの」と主張した。ただ同時に、特定のシナリオについてコメントすることは今後は慎むとした。
そして17日の定例会見で、中国外務省の毛寧報道局長は今週末に南アフリカで開かれる主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)に出席する李強首相が高市首相と会うかを問われ、「予定はない」と答えた。中国が早い段階で首脳同士の面会予定がないことを明らかにするのは異例だ。
●一線を越えた高市首相の発言
これが現在までの動きである。日本の主要メディアを見ると、高市首相の「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」という発言は極めて常識的で、中国側の過剰反応を非難する報道が目立つ。しかしBBCなど海外の報道を見ると、明らかに高市首相の発言は一線を越えたとの認識が多い。
高市首相の最近の発言は、台湾に関して日本が従来取ってきた不明確な立場からの脱却を意味するのだ。台湾をめぐっては、アメリカも長い間、「戦略的あいまいさ」を維持している。中国が台湾を侵攻した場合、アメリカが台湾を守るために何をするかは不明確のままにしている。このあいまいさが、何十年もの間、中国にさまざまな可能性を考えさせ、一種の抑止力となってきた。同時に、経済的な結びつきを発展させてきた。
アメリカのこのような立場に呼応するように、日本政府の公式な立場は、台湾をめぐる問題が対話を通じて平和的に解決されることを望むというものだ。日本政府関係者は通常、安全保障に関する公的な議論で、台湾に触れることを避けてきた。この意味で「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」という発言は、これまでの日本政府の立場から一歩踏み込んで武力行使の可能性を示唆するものだ。これは明らかに従来の方針からは一線を越えている。
●日本の従来の立場、1972年の「日中共同声明」
ここで大きな懸念は、高市首相がこのような発言がどのような事態を引き起こすのか、まったく無自覚に発言したことである。外交評論家で作家の佐藤優は、高市首相とトランプとの首脳会談の発言を見て「高市は外交音痴だ」と批判していたが、まさにこれは真実であったようだ。
では、台湾問題に対する日本の従来の立場はどのようなものなのか、ここできちんと確認しておこう。今後の状況を見るためにも、これは重要だ。
台湾問題に対する日本政府の従来の方針は、1972年に中華人民共和国との国交正常化の際に発表された「日中共同声明」が基本となっている。この声明に基づく日本政府の主要な立場は、以下の点に要約される。
1. 中国の立場への「理解」と「尊重」
日中共同声明の第三項には、以下のように記されている。「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」
ここで重要なのは、日本政府は中国の「台湾は中国の領土」という主張を「承認」するとは明記せず、「十分理解し、尊重する」という表現を用いている点である。これは、台湾の地位について日本独自の立場を留保する表現と解釈されている。
2. 非政府間の実務関係の維持
日本政府は、中華人民共和国を「中国の唯一の合法政府」として承認(日中共同声明第二項)して以来、台湾とは外交関係を断絶した。しかし、経済、貿易、文化、人的往来などの実務的な関係は重要であるとし、これらは「非政府間の実務関係」として維持されている。日本では「日本台湾交流協会」、台湾では「台湾日本関係協会」が、事実上の大使館機能(領事業務など)を担っている。
3. 平和的解決の希求
日本政府は一貫して、台湾をめぐる問題が武力によってではなく、中国と台湾の当事者間の話し合いを通じて平和的に解決されることを強く希望する、という立場をとっている。
ちょっと複雑になったが、要約すると、日本政府の従来の方針は、中国の「一つの中国」の原則(台湾は中国の一部という立場)を「理解し、尊重」するが、台湾とは非政府間の実務関係を維持し、「問題の平和的解決を望む」というものである。
一言で言うと、台湾問題に対する日本政府の従来の方針は、日本は「一つの中国」を認めはしないものの中国の立場を理解して尊重し、台湾問題の平和的解決を望むというものだ。このような日本の従来の方針から見ると、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」というのは、台湾問題で日本が武力行使の可能性を示唆したもので、明らかに一線を越えている。
中国の過剰な怒りの背景には、このような状況があった。そして、ここでもっとも危険なのは、高市首相はこの発言がもたらす影響を考慮せず、無自覚に発言してしまったことだ。もし高市首相が「日本の従来の方針は変わらない。平和的な解決を望む」と発言していたら、問題はなかっただろう。まさに高市首相は「外交音痴」なのだと思う。今後が大変心配だ。
●今後どうなるのか? 3つのシナリオ
今回の日中間の緊張は海外の専門家の間でも詳しく論評され関心が高い。ジョン・ミヤシャイマーとともに、アメリカの外交政策批判の巨頭、コロンビア大学のジェフリー・サックス教授を始め、今後どうなるのか複数の専門家が論評している。それらをまとめると、この問題の今後には、次の3つのシナリオがあるとしている。
1. 指導者レベルの制御された凍結状態の継続
第一のシナリオは、指導者レベルでの制御された凍結状態の継続だ。つまり、現状の継続ということだ。これが短期的に最も起こりうる結果である。中国は日本との首脳級会合開催を拒否し続け、この姿勢をG20以降も2026年初頭まで延長する。
閣僚級対話、予定されていた安全保障協議、防衛ホットラインは、スケジュールの都合で静かに延期または先送りされる可能性がある。中国は以前、韓国、オーストラリア、リトアニアに対して不満を抱いた際にも同様の戦術を用いた。戦略は単純だ。関係を断ち切らずに距離を置くことである。
日本にとって、このシナリオは既に代償が大きい。高レベルルートがなければ、日本は危機管理問題を中国と直接協議する能力を失う。東シナ海の不安定な状況や中国軍の大規模な海軍活動を考慮すれば、これは重大な問題だ。以前は上級レベルの連絡で対処可能だった小規模な海上インシデントが、政治的な火種となるリスクがある。
同時に日本は、中国国内の日本企業を支援する場も失う。これにより企業は規制上の遅延や突発的な調査にさらされやすくなる。しかしこうした代償にもかかわらず、経済的相互依存が続く限り、この制御された凍結状態は管理可能だ。官僚レベルの対話は継続し、双方は露骨なエスカレーションを避けることができる。
2. 外交的関与の選択的縮小
中国が長期的な経済的損害を招かずに圧力を強めたい場合、対象を絞った縮小措置を拡大する可能性がある。これには安全保障対話メカニズムの停止、共同海上調整チャネルの一時停止または凍結、検査や許可遅延を通じた日本企業への行政的圧力、中国人観光客の日本渡航制限などが含まれ、これらは中国が過去に韓国や台湾に対して用いた措置と類似している。
このシナリオでは、日本は二重の脆弱性に直面する。経済的依存度の高さと中国海軍活動への地理的近接性だ。観光客禁止措置だけでも、中国人観光客に依存する地域経済に数十億ドルの損失をもたらしうる。輸出主導型の日本の産業基盤は、通関遅延・市場参入障壁・突発的な規制強化といった中国における非関税障壁にも直面する可能性がある。
こうしたリスクにもかかわらず、日本は受動的ではいられない。日本は米国、EU、オーストラリア、アマゾンのパートナーとの連携強化で中国の圧力に対抗するだろう。サプライチェーンの多様化が加速する。高市政権は台湾に関する発言をさらに強める可能性すらある。中国の強圧的行動がより厳しい姿勢を正当化すると主張するのだ。
このシナリオは断絶には至らないものの、日本の他の民主主義国との長期的な連携強化や日中の安定共存可能性の縮小を通じ、戦略環境を大きく変える。
3. 深刻な外交関係悪化あるいは一時停止
可能性は低いものの、緊張が継続的に高まる場合、特に台湾関連の言説が激化したり、尖閣諸島付近で海上衝突が発生したりすれば、この極端なシナリオも完全に否定できない。
外交関係の格下げには、大使召還、領事館閉鎖、高レベル経済会合の中止、文化・学術交流の縮小が含まれる。1972年の国交正常化以降、中国と日本にとって前例のない、かつて中国が小国に対して行ったような外交関係完全断絶となる。
日本への影響は甚大だ。中国に依存するサプライチェーンは即時混乱に陥る。日本の自動車メーカー、電子機器メーカー、化学メーカーは深刻な損失を被る可能性がある。外交ルートによる抑制が失われることで、東シナ海における軍事的緊張はエスカレートするだろう。
中国にとって、安定した貿易相手国である日本を失うことは、国内経済の不確実性の中で成長を安定させようとする中国の努力を損なう。日本が欧米の同盟国との統合を加速させることは、アジアにおける米国の影響力を強化し、まさに中国が阻止しようとしている事態を招く。予測可能な経済パートナーとしての中国の国際的評価は打撃を受けるだろう。
要するに、双方とも多大な代償を払うことになる。このシナリオは相互破壊的な結果であり、中国も日本も究極的には望まない結末だ。
●問題は見かけよりも深刻
これらのシナリオを通じて明らかになるのは、現在の危機が単なる一言の発言や会談拒否の問題には止まらないということだ。台湾が地域地政学の焦点となったこの時点で、日中関係の構造的脆弱性が露呈しているのだ。
中国がG20出席を拒否したことは、最初の目に見えるサインだ。しかし、その後の展開が、これが一時的な外交的冷え込みに終わるのか、それとも東アジアにおけるより深い戦略的亀裂の始まりとなるのかを決定する。首相会談の拒否は、中国が今や日本に対して優位な立場から行動していることを示唆している。
この認識は、中国が会談を断りながらも関係安定化に焦りを示さないその自信に起因する中国の強みは規模、市場力、そしてナショナリズムの動員力にある。最も明白な影響力の源泉は経済規模だ。中国の市場、特に国内消費の基盤は、依然として日本よりも規模が大きく戦略的に重要だ。中国が不快感を示せば、正式な制裁がなくても主要な外国企業は圧力を感じる。
日本の中国への依存、産業投入物資や製造業におけるサプライチェーンは容易に代替できない。中国はこのことを十分に理解しており、強気の態度を崩す兆候はない。
さて、このように見ると、今回の問題は時間が経てば自然と解決するというものではないことは明らかだ。予想以上に深刻なのだ。おそらくこの解決策のひとつは、高市首相が国会で、日本は一つの中国を認めており、台湾問題の平和的な解決を望むとする従来の方針を改めて明確に強調することだろう。中国の方から態度を軟化すると思ってはならないだろう。今後、どうなるか注目だ。これから数週間が重要な別れ道になるだろう。
* * * * * * * * *
●「ヤスの勉強会」第141回のご案内●
「ヤスの勉強会」の第141回を開催します。高市首相の思わぬ発言から日中関係が大変に緊張しています。これからどうなるのでしょうか? また、エプスタインリストの公開でトランプもレイムダック化しています。ベネズエラで戦争を始め、国民の関心をそらそうとする可能性もあります。混沌とした世界ですが、何が本当に起こっているのか、あらゆる情報を駆使して徹底して分析します。
※録画ビデオの配信
コロナのパンデミックは収まっているが、やはり大人数での勉強会の開催には用心が必要だ。今月の勉強会も、ダウンロードして見ることのできる録画ビデオでの配信となる。ご了承いただきたい。
【主な内容】
・日本のこれから、いったいどうなるのか?
・レイムダック化するトランプ
・経済危機のリアルな可能性を検討する
・中国の実態
・変化するBRICSの国際秩序
・テック・ライトの最終計画とは?
・コルマンインデックスと我々の意識
など。
よろしかったらぜひご参加ください。
日時:12月27日、土曜日の夜までにビデオを配信
料金:4000円
懇親会:リアル飲み会とZOOMで開催
以下のメルアドから申し込んでください。
記載必要事項
名前(ふりがな)
住所 〒
メールアドレス
参加人数
懇親会の参加の有無
ytakashima@gmail.com
…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
■ヤスの備忘録 歴史と予言のあいだ
http://ytaka2011.blog105.fc2.com/
■未来を見る!『ヤスの備忘録』連動メルマガ 毎週金曜日配信
http://www.mag2.com/m/P0007731.html
■ツイッター
https://twitter.com/ytaka2013/
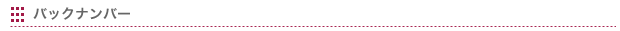
| 26/01 | |
| 25/12 | |
| 25/11 | |
| 25/10 | |
| 25/09 | |
| 25/08 | |
| 25/07 | |
| 25/06 | |
| 25/05 | |
| 25/04 | |
| 25/03 | |
| 25/02 | |
| 25/01 | |
| 過去年 | |


社会分析アナリスト、著述家、コンサルタント。
異言語コミュニケーションのセミナーを主宰。ビジネス書、ならびに語学書を多数発表。実践的英語力が身につく書籍として好評を得ている。現在ブログ「ヤスの備忘録 歴史と予知、哲学のあいだ」を運営。さまざまなシンクタンクの予測情報のみならず、予言などのイレギュラーな方法などにも注目し、社会変動のタイムスケジュールを解析。その分析力は他に類を見ない。
著書は、『「支配−被支配の従来型経済システム」の完全放棄で 日本はこう変わる』(2011年1月 ヒカルランド刊)、『コルマンインデックス後 私たちの運命を決める 近未来サイクル』
(2012年2月 徳間書店刊)、『日本、残された方向と選択』
(2013年3月 ヴォイス刊)他多数。
★ヤスの備忘録: http://ytaka2011.blog105.fc2.com/
★ヤスの英語: http://www.yasunoeigo.com/