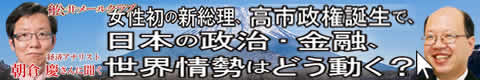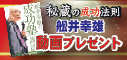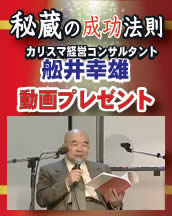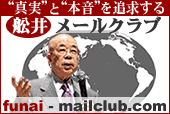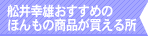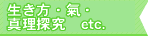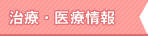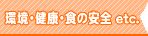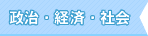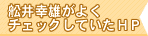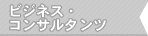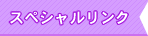“超プロ”K氏の金融講座
このページは、舩井幸雄が当サイトの『舩井幸雄のいま知らせたいこと』ページや自著で、立て続けに紹介していた経済アナリスト・K氏こと
朝倉 慶氏によるコラムページです。朝倉氏の著書はベストセラーにもなっています。
「今年の賃上げ率は30年ぶりの水準になったが、それ以上の物価高で実質賃金が上がっていない。今年以上の結果が出る取り組みを進めていきたい」
10月19日、連合の芳野会長は来年の賃上げ要求について連合として積極的に取り組んでいくことを公言しています。
そして連合は来春の賃上げ要求を「5%以上」の要求とすると発表しました。今年の要求は「5%程度」でしたから、連合は来春の春闘は今年以上の要求を行うということです。一般の人から見れば、これでも要求は控え目のような気もします。
というのも、食料品をはじめとする生活必需品の値上がりは明らかに10%を超えているというのが庶民の肌感覚です。統計で出てくる消費者物価の上昇率は2.8%ということですが、そんな低い上昇率と感じている人は日本中探してもいないでしょう。どの値札をみても値上がりするばかりで、庶民の生活は厳しさを増すばかりです。
当然、給料も物価高に追いつくような水準にまで上がらなければやっていけません。日本で最大の労働組合である連合がこの時点で来春の賃上げの目標額を「5%以上」と発表したことは心強いと思います。
この5%という賃上げ目標に対して「なぜ6%以上にしなかったのか?」という声も上がっています。実際、米国などでは自動車組合の労働者などは4年で20%の賃上げという経営側の回答を、「話にならない」とはねつけて未だにストを続けています。因みに労働組合側の要求は4年で40%という「年間10%ずつ賃上げを行え」というものなのです。人手不足が酷い米国のパイロット組合などはかような水準で経営側と交渉が成立しています。
年間10%近い賃上げを4年間も保証されるのですから、やはり米国は何事に対してもスケールが違うと思ってしまいます。
●日本での賃上げの推移
日本も米国のように労働組合が過激な時代もありました。石油ショックが起こった1974年の春闘における労働組合側の賃上げは何と33%というとてつもない賃上げを勝ち取ったこともあったのです。因みにこれほど賃上げを進めては、会社の経営がおかしくなってしまうということで、この1974年をピークとして労働組合側の賃上げ要求も下火になっていくようになりました。
しかしながら日本において本格的に賃上げがなくなってきたのは、2000年代に入ってからでした。
というのも、この2000年には中国がWTO(世界貿易機関)に参加します。
WTOに参加するということは、この時点から中国が世界と積極的に交流をし始めたということで、この時から中国経済が世界経済に組み込まれていったというわけです。
わずか23年前ですが、当時の中国は貧しく、国民の多くは貧困層ばかりでした。これらの人々は都市に出稼ぎに出ていって、工場労働者として働くようになっていきました。こうなると日本労働者はとても中国の労働者に太刀打ちできません。当時の日本は賃金が高いし、当時の中国は日本の数分の1の給料ですから、日本の労働者は競争に勝てないわけです。
当時、やはり中国の膨大な労働力と安い賃金は魅力で、2000年から日本企業は次々と中国はじめ東南アジアなどにも進出、結果、日本の労働者は賃金が極めて割高ということなり、企業としても日本の労働者を高給で雇用していてはとても国際的な競争に勝てないという現実に直面することとなりました。
これでは日本の企業はとても生き残れないというわけで、日本の大企業はその業績が極めて好調であったとしても労働者に対しての賃上げを拒否するようになりました。
典型的なケースがトヨタで、トヨタは当時から業績好調で日本で一番の利益を叩き出し、日本で一番儲かっている会社だったのですが、何と賃上げを拒否、「ベアアップなどとんでもない」と公言するようになったのです。
日本で一番儲かっていた会社が賃上げしないのであれば、どんな会社が賃上げできるというのでしょうか? この2000年代前半は日本全体、労働組合はじめ労働運動は極めて下火となって、労働組合も賃上げを要求することはあきらめて、何とか雇用を確保してほしいと経営側と交渉するような事態に至ってしまったわけです。
かように日本の賃上げは全く忘れられてしまったのですが、2012年発足した安倍政権は、金融緩和と共にインフレ政策を断行していきましたので、安倍政権として企業側にも賃上げ要求をするようになりました。
これは大きな変化でした。従来政府はストライキなど労働争議が激しくなると、国が混乱するので、労働組合に対しては、その運動を抑えるように取り組むものです。ところが、安倍政権下では政府が率先して経営側に賃上げを迫るのですから、極めて不思議な構図となっていったわけです。
しかしながら、日本は長くデフレが続いた関係で、この政府が労働側と一緒になって、経営側に賃上げを迫るという構図は、現在の岸田政権下においても続いているということなのです。
10月5日、岸田首相は日本の首相として16年ぶりに連合の定期大会に出席しました。一国の首相が労働組合の大会に出席するというのは極めて異例です。
自民党でなく、労働組合を支持基盤とする立憲民主党や国民民主党の党首が出席するのはわかりますが、何と自民党総裁で首相である岸田氏が労働組合の大会に出席したわけです。世の中も大きく変わったものだと感じさせます。
岸田首相は「経済の好循環を実現するために連合とコミュニケーションを取りながら全力で取り組んでいく」と連合にエールを送りました。
かような情勢下では、日本においても賃上げが実現するのは当然の流れと思います。
一方、賃上げを行う経営側ですが、経団連の首脳は「業績は悪くない、少なくとも物価を超える水準を続けなければ賃上げの意味はない」と賃上げに前向きな発言を行っています。
また経団連の十倉会長は「連合が来年の春闘で賃上げ目標を5%以上としたのは理解できる」として「賃上げを今年1回限りで終わらせず、引き続き最大限の熱量で呼びかけていきたい」とまで述べています。
政治側はトップの岸田首相、経営側は経団連トップの十倉会長、そして労働組合側もトップの芳野会長は各々、5%賃上げを叫んでいるのですから、来春の春闘での大幅賃上げ実現は当然の流れでしょう。
●これからはインフレ時代
朝倉はこのコラムでも一貫して主張してきたことは、日本が大きく変わってインフレ時代に入ってきた、これからはすべてのものが上がっていく、今までのデフレ時代とは全く違ったインフレ時代となる、賃金も上がり続けると主張してきましたが、今の日本はそのようにインフレに向かって一直線に進んでいく傾向です。
そもそも法人企業統計によれば、資本金10億円以上の大企業の2022年の経常利益は15%増です。また2023年4-6月期の経常利益は9%増です。これらの業績を見る限り簡単に5%の賃上げはできるのです。ですから既にサントリーなどは今年に次いで来年も7%の賃上げを公表しています。日本の大企業は次々に追随していくでしょう。
一方、苦しいのは中小企業です。円安による物価高、人手不足による人員確保の難しさ、そしてゼロゼロ融資の返済など厳しい局面に立たされています。
実は連合としても6%以上の賃上げ要求を掲げたかったのですが、それが出来なかったのは、中小企業に考慮したからでした。日本の中小企業を中心とした団体である日本商工会議所の小林会頭は「可能な限り賃上げを進めたいと思うが、5%以上の大幅な引き上げは難しいのでは」と中小企業の立場を考慮して大幅賃上げ要求に懸念を表明しています。
この辺りがインフレ時代の苦しいところです。円安が進み、ついにドル円相場は150円台に突入しています。日本ではますます物価高が激しくなっていくでしょう。物価高となれば働いている人の給料も上げてやらないとまずいわけです。しかしながら収益が上がらなければ給料も払えません。最終的にこのインフレ時代に生き残れる企業と残念ながら淘汰されてしまう企業が出てくるわけです。インフレ時代の到来は我々に過酷な現実を見せつけていくのです。
■□-----------------------------------------------------------------□■
★「ASAKURA経済セミナー」
音声ダウンロード、CD、DVDを販売中!
ご自宅にいながらセミナーを受講。
お好きなときに、お好きな場所でお聴きいただけます。
●収録時間 約3時間
●価 格
【DVD版】16,000円(税込)
【CD版】13,000円(税込)
【音声ダウンロード版】13,000円(税込)
※音声ダウンロードはEメールでお届けするので、一番早くお届けできます◆
→https://www.ask1-jp.com/shopping/study/seminar_media.html
■□-----------------------------------------------------------------□■
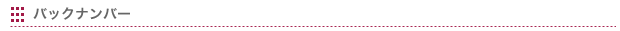
| 25/12 | |
| 25/11 | |
| 25/10 | |
| 25/09 | |
| 25/08 | |
| 25/07 | |
| 25/06 | |
| 25/05 | |
| 25/04 | |
| 25/03 | |
| 25/02 | |
| 25/01 | |
| 24/12 | |
| 24/11 | |
| 24/10 | |
| 24/09 | |
| 24/08 | |
| 24/07 | |
| 24/06 | |
| 24/05 | |
| 24/04 | |
| 24/03 | |
| 24/02 | |
| 24/01 | |
| 過去年 | |


★『大恐慌入門』
(2008年12月、徳間書店刊)に引き続き、『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)が2009年5月に発売。その後 家族で読めるファミリーブックシリーズ『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)が同年5月30日に発売。さらに2009年11月には、船井幸雄と朝倉氏の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)が発売され、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を、2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を発売、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
を発売、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/
 経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』
経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』(2008年12月、徳間書店刊)がアマゾンランキング第4位を記録し、2009年5月には新刊『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)および『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)を発売。2009年11月に舩井幸雄との初の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を発売。2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/