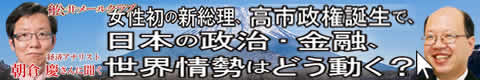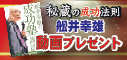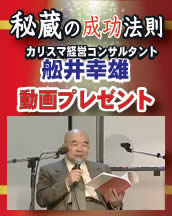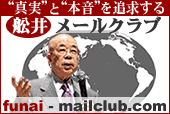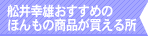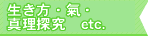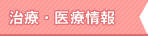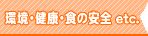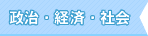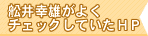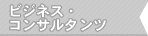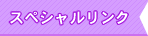“超プロ”K氏の金融講座
このページは、船井幸雄が当サイトの『船井幸雄のいま知らせたいこと』ページや自著で、立て続けに紹介している経済アナリスト・K氏こと
朝倉 慶氏によるコラムページです。朝倉氏の著書はベストセラーにもなっています。
日本では1989年暮れのバブル崩壊から、何と20年以上にわたって基本的には株式市場の低迷が続いています。この間、いろんな投資話はありましたが、基本的には国債かないしは低利ですが、元金保証の預金、並びに現金で資産を保有していた人が救われたのです。
一般的に日本人は投資に関しては保守的ですから、世間で言われているように金利が安い、不景気で困ったという問題はあるものの、日本人のマジョリティーは、この20年というデフレの期間、財産管理は完ぺきとは言えないまでも、それほど酷い状態にはなっていなかったのではないでしょうか? グローバル・ソブリン・ファンドとか外債とか株とか、投資話に乗った人達が火傷を負ったものの、日本人の大半はこのデフレ期で実質資産を減らすことはなかったというところが大勢だったと思えます。これはお堅い預金好きの日本人の保守性が時代にはマッチして財産保全という意味では功を奏していたということでしょう。
日本の国家破綻は近い!?
しかし私はもうこのデフレの時代の終焉も近いと思っています。
昨年、東日本大震災で思わぬ悲劇が東北地方を襲いました。真面目に生きてきた人々も理不尽に命を落としたのです。津波が容赦なく人々を飲みこんでいきました。私はたえず著作で警告を続けてきましたが、日本の財政はどう考えても持続不能で、国債の暴落から日本の国家破綻が来る日も近いと確信しています。
その時はまさに、全日本国民に容赦なく経済津波が押し寄せて人々の財産を奪い去っていくことでしょう。この時は、今まで保守的で堅く、現金並びに預金、国債などで資産を保有してきた人々は、その資産をインフレによって実質的にほとんど失う局面が訪れると思っています。まさに理不尽な津波に東北の人々が流されたように、日本人の資産も経済津波と共に消え去ってしまうことでしょう。
この劇的なタイミングがいつか? ということは難しい判断になりますが、私は、もう現金などの資産はそれほど多く持たずにいわゆる現物資産、株、不動産、金や貴金属などに資産をシフトすべきであると思っています。
ここで、最近の国家破綻の例を見て、国家破綻した国々でどんなことが起こったか? ということを株や物価、賃金などの動きを比較してみてみたいと思います。まずはアフリカ南端の国、ジンバブエの例です。ジンバブエでは、1兆倍という激しいインフレに陥って経済が破綻しました。これは有名なドイツの第1次世界大戦後の賠償金支払いによる大インフレに匹敵するケースです、このケースを追ってみましょう。
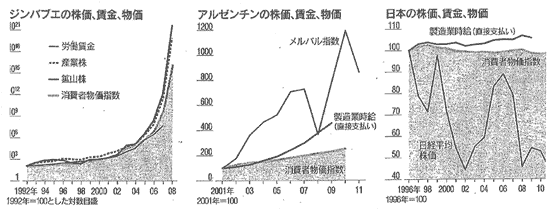 ジンバブエ、アルゼンチン、日本の株価、賃金、物価の推移(※クリックすると拡大して見られます。) 資料:日経ヴェリタス(12/4) |
日経ヴェリタス(12/4)の資料によれば、ジンバブエの消費者物価はインフレが酷くなった2006年末から2008年7月末にかけて15億倍になりました。
一方その間、70銘柄で構成されるジンバブエの産業株指数は同じく2006年末から2008年11月19日にかけて1兆倍強になったのです。さらに4銘柄で構成される鉱山株指数は同期間に17兆倍へとなりました。百貨店を経営するメイクルズの株価は2007年末の0.00085ジンバブエドルから2008年11月19日には10京5,000兆ジンバブエドルへと上昇しました。余りに単位が変わり過ぎてピンときませんが、京の単位は兆の上になりますから、その京の単位の上にまで上昇した株もあったということで理解すればいいと思います。
2008年11月19日というのは、ジンバブエではその日まで株が現地通貨ベースで取引がなされていたということで、この日を最後に取引所は閉鎖、翌2009年2月18日に、米ドルベースで取引再開となったわけです。
資料(グラフ1)で示したように、このハイパーインフレの間、労働賃金よりも消費者物価の上昇率が高く、さらには消費者物価の上昇率よりも産業株指数の上昇率の方が高く、さらには株では、鉱山株指数が産業株指数よりも高くなったことは注目です。
日本が仮に財政破綻から国家破綻に陥った時に、株や不動産、現金など資産ベースの動きはどうなるか? というのは正確に予想するのは難しいところですが、このジンバブエにおけるインフレ爆発時の労働賃金、消費者物価、産業株指数、鉱山株指数の比較は参考になるところです。
ハイパーインフレ時に、株の保有は有効?
常識的に考えても、インフレに対応できるのは国際的に通用する企業群です。特に鉱山株などの資源株はインフレには大きく反応しますし、マネーの価値が無くなる過程でその価値が他の資産に比べて暴騰状態になっていったのは注目で、日本のケースでも同じことが起きると考えられます。また産業株指数が消費者物価を凌駕したことも注目です。当然、1兆倍という激しいインフレでは、経済は完全に破綻しているわけで、その間、多くの企業が立ち行かなくなり、倒産状態に陥っていったと想像されます。その情勢にあって、代表的な産業株指数が消費者物価を凌駕した事実は、このようなハイパーインフレ時には株の保有は極めて有効であることを示していると言えるでしょう。70銘柄で構成された産業株指数ということは、その企業群の中には倒産した企業や倒産すれすれの企業、また、インフレに乗じて利益を得た企業もあったことでしょう。それらの平均値として、株式が消費者物価の600倍になったことは興味深い事実です。明らかに、インフレ時の株式投資の有効性を物語っていると言えるでしょう。またジンバブエのケースでは、海外に株式を上場していた企業もインフレの影響を免れました。
次に2001年12月にデフォルト宣言をして国家破綻したアルゼンチンのケースを見てみましょう(同グラフ1参照)。アルゼンチンは国家破綻した2001年12月末、株式指数であるメルバル指数は295ポイントでした。これが10年経って、2011年1月には高値3700ポイントまで約12.5倍に急騰したのです。この間、当然国家破綻ですからインフレ状態となったわけですが、消費者物価は10年間で2.5倍ということです。このケースでも株は完全に消費者物価を凌駕しています。
面白いことですが、アルゼンチンの株価をみると、アルゼンチンが国家破綻をした2001年末から上昇が始まってきたのです。それに至る1996年から2001年末までの5年間は、株価は半分弱に暴落していたのです。これも興味深いケースです。普通であれば国家が破綻したわけですから、そこから株価は奈落の底に落ちていくようなイメージを抱きます。ところが逆なのです。国家破綻するまでは株価は下げ続け、破綻した後は、10年に渡る上昇相場の始まりとなったわけです。この事実にはどうして? と不思議に思うかもしれません。ところがこれこそが株式市場の持つ先見性というものです。
国家破綻になれば企業が潰れていくのは当然ですが、それ以上の激しいインフレが襲うということもあるわけです。アルゼンチンの株価はこのインフレを予見して、国家破綻直後から上昇が始まったというわけです。そしてその後、10年間で株価が完全に消費者物価を4倍も凌駕して上昇しているのは興味深いところです。
日本ではもう、資産を株や不動産にシフトすべき時期?
翻って日本はどうかといいますと、これはアルゼンチンが国家破綻するまでの5年間に株価が下がり続けたケースと似たような段階にあると思います。ヴェリタスの解説によれば、日経平均は1996年末を100とすると、2011年末には44まで下落してまさに半値以下です、その間消費者物価は1.5%の下げ、まさにデフレです。そして労働賃金は5%近い上昇だったのです。こう見ていくと、この1990年台から2011年までは現金並びに国債を保有していた人達だけが損することもなく、デフレに対応してマネーの価値を維持していたことが見てとれます。
しかし今後、日本は持続不能な財政から国家破綻に陥っていくのは必至と思います。その時は今までの投資スタイルが100%変わって、インフレに随時対応できる株式投資の必要性が高まってくるものと思います。一般的には庶民の暮らしは厳しいこととなるでしょうが、その極めて苦しい不景気の中で、株は恒常的なインフレを受けて上がり続けるでしょう。財産3分法とは昔からの習えですが、私は国家破綻秒読みのこの局面では、もう株や不動産に資産をシフトすべきで、これらの上昇の流れは10年単位で続く可能性があると思います。終戦後、1945年から1989年まで株も土地も上がり続けました。まさに日本はインフレ、経済発展の時代だったのです。
そして1990年初頭から、バブル崩壊、衰退への道が始まったのですが、国家の借金、国債の無尽蔵の発行、借金生活で漬けを貯めていきます。この間はデフレの時代です。そしてこの借金生活が強制的に国家破綻によって不可能となります。その瞬間から今度は、悪性のインフレが始まってくる長いインフレのトレンドに入ると考えるとどうでしょうか? こうしてインフレからデフレ、デフレからインフレへと日本は根本的な変化を体験するわけです。当然それに応じた資産運用が重要です。
こうして今、お堅い投資で現金だけ、国債だけを保有してきた日本のほとんどの人達が今度は資産保全の対応に苦慮する時代が訪れることでしょう。
バブル崩壊に戸惑って、また株が上昇する時が来ると信じて大きな損失を抱えた投資家達、彼らの身になってみればわかりますが、人間というものは弱いもので、同じトレンドが1945年から1990年へと45年間も続いたら考えも変化させることはできません。成功体験があった人はなおさらです。同じように20年にわたって続いたデフレの時代の記憶は、今の人達にとっては抜け出すことのできない身にしみついた経験でしょう。しかし、永遠に続く流れなどないのです。インフレが来てデフレがきて、またインフレが来て経済は繰り返します。「賢者は歴史に学び、愚者は体験に学ぶ」と言いますが、変化の歴史を感じ取った人達だけがこれからの時代の勝利者となっていくことでしょう。
では、どのような金融機関に資産を預ければ安全といえるでしょうか? 一般的に考えれば大手の金融機関が安全ということになります。それはそうかもしれません、たとえば三菱東京UFJですが、このような日本一の金融機関が仮に倒れるようなことがあれば、日本は国家として立ち行かなくなってしまいます。いうならば、主要金融機関は日本そのものと言えるでしょう。しかし、一方で、仮に国債の暴落が起これば、日本の銀行や生損保はそのほとんどがこの国債投資に依存していますから、財務的には全滅という事態に陥っていきます。こう考えると国債が暴落した地点では預金封鎖するか、あるいは日銀が無尽蔵のマネーを刷って対応するしかありません。どちらのケースも激しいインフレです。
国債暴落の影響が比較的軽微な金融機関は?
一方、主要金融機関の中にあって、この国債暴落の影響が比較的軽微ですむのは、ネット銀行です。これは国債を多くは持っていません。主に決済業務だけで収益をだしています。そして証券会社です。証券会社は日本の場合は、その収益は大半が手数料に依存しています。株式や投資信託、外債などの販売手数料で経営が成り立っているわけです。これらネット銀行や証券会社なども国債暴落という大混乱になれば、不測の事態が訪れる可能性もあります。ただこのケースで、直接この国債を保有していないといことは強みです。銀行や生損保は国債が暴落してしまえば、預かった資金が無くなってしまいますが、証券会社の場合は分別管理といって国の指導で顧客資産と自分の会社の資産は別勘定になっています。そういう意味では国債の暴落のような大パニックに安全なのは日本の場合は証券会社と言えるかもしれません。
もう少し、銀行と証券会社の収益構造を考えるとわかります。銀行や生損保は預かった資金を運用して利益を得ているわけです。いわば顧客からのお金を自己勘定で運用しているわけです、ですからこの運用に失敗すれば資金が残りません。これが金融危機ということです。ところが日本の証券会社は顧客の資産を預かっているだけです。その顧客が株を買おうが投信を買おうが国債を買おうが、証券会社はその時に手数料をいただくだけです。証券会社が昨今のように手数料収入の激減から赤字になることはありますが、日本では分別管理で、顧客の資産と証券会社の資産は別管理ですから顧客の資産は常に存在しているわけです。もちろん混乱で株や投信が大幅な暴落ということはあります。しかしその資産が消えることはありません。
| 12/12 | |
| 12/11 | |
| 12/10 | |
| 12/09 | |
| 12/08 | |
| 12/07 | |
| 12/06 | |
| 12/05 | |
| 12/04 | |
| 12/03 | |
| 12/02 | |
| 12/01 |
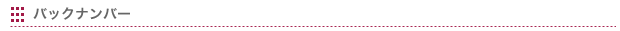
| 25/12 | |
| 25/11 | |
| 25/10 | |
| 25/09 | |
| 25/08 | |
| 25/07 | |
| 25/06 | |
| 25/05 | |
| 25/04 | |
| 25/03 | |
| 25/02 | |
| 25/01 | |
| 24/12 | |
| 24/11 | |
| 24/10 | |
| 24/09 | |
| 24/08 | |
| 24/07 | |
| 24/06 | |
| 24/05 | |
| 24/04 | |
| 24/03 | |
| 24/02 | |
| 24/01 | |
| 過去年 | |


★『大恐慌入門』
(2008年12月、徳間書店刊)に引き続き、『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)が2009年5月に発売。その後 家族で読めるファミリーブックシリーズ『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)が同年5月30日に発売。さらに2009年11月には、船井幸雄と朝倉氏の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)が発売され、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を、2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を発売、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
を発売、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/
 経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』
経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』(2008年12月、徳間書店刊)がアマゾンランキング第4位を記録し、2009年5月には新刊『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)および『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)を発売。2009年11月に舩井幸雄との初の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を発売。2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/