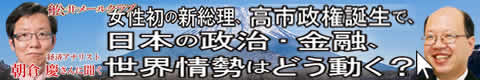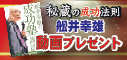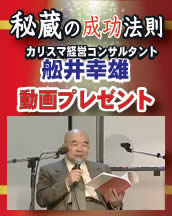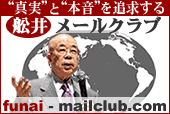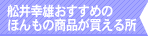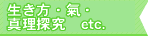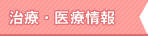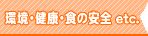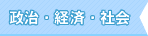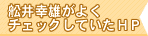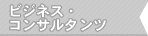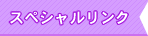“超プロ”K氏の金融講座
このページは、舩井幸雄が当サイトの『舩井幸雄のいま知らせたいこと』ページや自著で、立て続けに紹介していた経済アナリスト・K氏こと
朝倉 慶氏によるコラムページです。朝倉氏の著書はベストセラーにもなっています。
「独自の通貨を持つ国の政府は、通貨を際限なく発行できるため、デフォルト(債務不履行)に陥ることなく、政府債務残高がどれだけ増加しても問題ない」
面白い新しい金融理論が米国から発信され、欧州はじめ世界で話題になりつつあります。通貨を独自で発行できる国、米国はドル、日本は円、中国は元、数えればきりがないですが、世界中のほとんどの国がそうだと思いますが、そのように通貨を発行できる国であれば、その国において政府の借金をいくら膨らませても一向に問題は起きないというのです。
一見して考えれば「国の借金お構いなし」というかようなメチャクチャな金融理論はありえないと思われますが、これが真剣に議論され始めているのです。しかも来年の米国大統領選挙において米民主党の有力候補と思える議員や、先に米国下院議員として最年少で議員となった今や全米マスコミ注視の的となっている、アレクサンドリア・オカシオ・コルテス氏などがこの金融理論を積極的に支持、米国から世界へと急速に話題になってきました。
●現代金融理論(MMT)とは
この理論は現代金融理論(MMT)、分解するとModern(現代)、Monetary(金融)、Theory(理論)という立派な理論体系になっています。提唱者の一人はニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授です。彼女によれば、例えばギリシアのような独自の通貨を持たずにユーロという共通通貨を使用しているケースでは、自らの判断で無制限にマネーの流動性供給を行うことができないわけで、そうなればやむなくデフォルトに陥るリスクが存在する。
一方で独自に発行できる通貨があれば通貨を発行すればいいわけだから、デフォルトに陥ることはありえない、というわけです。ただし条件としては、「政府債務の増加がマクロ的な供給不足からインフレを起こすような場合でない」ことで、現在の米国のように経済成長と雇用の増加が続いている限り、政府債務の増加自体は問題ないというのです。
この「インフレを起こすような場合でない」という条件があいまいで、その判断が極めて難しいところですが、この理論が米国の政治家に受け入れられつつあるところがミソです。
「いくら国が借金しても構わない」というかような都合のいい理論が真剣に議論されるということは、現在の世界的な政策的な手詰まり状況をそれなりに写しているわけです。それは世界を見渡して、金融政策自体が限界に近づいてきていて、どの国も取るべき金融政策が難しくなってきているということがあります。
例えば、日本のことを考えてみましょう。日本の金融政策は日銀が行うわけですが、日銀は2000年から量的緩和政策ということで、円紙幣を印刷して日本国債を購入することを過去20年近くに渡って続けてきました、特に黒田総裁がトップに就任した2013年からは異次元緩和政策と銘打って国債購入額を劇的に増やしました、日銀はインフレ目標2%達成を公言、その達成に向けて必死になっていたわけです。その異次元緩和政策ですが、2%のインフレ目標は達成できず、今では有名無実化してしまいました。黒田総裁は年間80兆円日銀が日本国債を購入すると宣言、それを実行していたわけですが、今は完全にペースダウンです。実は日銀は数年に渡って日本国債を買いすぎてしまったために、市場に国債がなくなってしまったのです。そのために年間80兆円購入するというアナウンスは現在単なるお題目となってしまい、今では年間30兆円強購入する程度のペースにまで落ちてきています。いわば日銀は今でも異次元緩和政策とはいうものの、実質的にはかつての緩和政策は維持されていないのです。というか維持できなくなったわけです。一連の流れは日本の金融政策の限界を示しているとみられています。
理論的に考えれば、やる気になれば日銀はかつてのアナウンス通り年間80兆円の国債を購入することも可能かもしれませんが、そうなると国債は市場にほとんどないので、かなり高い値段をつけて購入するしかなくなるわけです。そうなると現在でも日本国債10年物、これは日本の長期金利ですが、それがマイナス0.09%にまで金利低下となっています。さらに無理して日銀が国債購入を拡大していけば、このマイナス金利幅は拡大していきます。そうなると金利のマイナス状態が恒常化してしまいます。さらにマイナス幅の拡大に歯止めがなくなる可能性もあります。そうなってしまっては、今でも厳しい銀行の経営がさらに窮地となってしまうわけです。これでは銀行の経営状態が全体的に悪化して金融システム全体に及ぼす影響が深刻となる可能性が高いのです。かような日本全体の銀行の危機的状況は看過できません。勢い日銀としても量的緩和政策を緩めるしかなかったのです。日銀の政策的な手づまり状況は日本における金融政策の限界を露わにしたのです。
欧州でも日本と似た様な状況になっています。ECB(欧州中央銀行)は量的緩和政策で域内の国債を積極的に購入し続けたのですが、かような量的緩和政策を長く続けるうちにドイツ国債はじめ、日本のケースと同じく域内の国債が買い尽くされて国債が枯渇状態となってしまいました。購入すべき国債がなければ、ECBがユーロ紙幣を印刷して国債を購入するという量的緩和政策は成り立ちません。こうして日本でも欧州でも量的緩和政策は行き詰まってきたわけです。
米国でも昨年暮れまでは金利は、今後2年くらい引き上げ方向とみられていました。ところが今年になって状況は一変、早くも金利引き上げ打ち止めで、今後は金利引き下げ観測が広がってきているわけです。米国においても以前のように金利を大きく上げていくことが難しい情勢になってきているわけです。かように日欧では量的緩和策が行き詰まり、米国では予想外に早く金利引き上げも終了です。今や金融政策の常識がかつてと比べて変わりつつあり、金融政策をダイナミックに展開することが世界的にも難しくなってきているのです。かような情勢変化を受けて、金融政策に変わって政府が積極的に資金を供給していくという財政政策が注目されるようになってきました。
そして米民主党議員の支持をみてもわかるように、この財政政策の拡大、いわゆるバラマキ政策はどの国でも人々の支持を受けやすいわけです。特に米国の民主党議員は前回のこのコラムで書いたグリーン・ニューディール政策とか国民皆保険制度とか、膨大な資金を必要とする政策を前面に打ち出してきています。この場合、当然のことながら政府の使う資金に際限がなくなっていくわけです。ところが政府がかように無節操に借金して資金を使い続ければ、当然将来的なインフレ到来、放漫財政によってバラマキを続けたために通貨の信用を失ってインフレが生じてくる、という懸念も危惧されるわけです。ですから普通は財政規律を守るとか、バラマキ政策はやめるとか、政府支出を削減するというような政策的な歯止めをかけてきたわけです。
そのような歯止めを取り払う上手い考えがここで登場してきた現代金融理論(MMT)というわけです。このMMTを採用すれば都合のいいことに、いくら政府が借金しても構わないというわけです。これが理論的な支柱となって民主党議員としてはグリーン・ニューディール政策も推し進めることができますし、国民皆保険も実現することができます。インフレになったらどうするのか、という懸念に対してはMMTという理論を前面に出すことによって、大丈夫と説得すればいいわけです。
というわけでこの都合のいい理論であるMMTに対しての人気は高まる一方なのです。欧州でもユーロ圏は厳しい財政規律が採用されています。
これに対して南欧諸国は緊縮財政を嫌い、財政の拡大を要求しています。イタリア政権は極右と極左の連合政権ですが、この政権もMMTの理論に共感しているのです。イタリアの場合はユーロ圏ですから、使用している通貨がユーロなのでMMTのような政策の実現は難しいかもしれませんが、5月に行われる欧州議会選挙で欧州議会の構図が劇的に変わるようなことがあれば、ユーロ圏においてもバラマキ政策を採用する政策的な変化が起こるかもしれません。
●賛否両論、広まるMMT議論
注目は今後の大統領選に向けた米国の状況です。今のところトランプ大統領はマスコミに嫌われ全米各地で反発も強いですが、一方で根強い熱狂的なトランプ支持もあります。2020年の大統領選挙の帰趨はわかりませんが、民主党候補者の中で有力な候補者が現れて、その候補者がMMT理論を前面に打ち出して選挙戦を戦って、その結果勝利するというケースもあるかもしれません。そうなると米国において本当にかようなMMTという過激な理論が実践される可能性もゼロではないわけです。
MMTの議論において、「財政赤字は問題無し」という理論的な証左となっているのは日本のケースです。日本はGDPの250%近い国の借金がありながら、財政再建は行わず、借金財政を止めどもなく続けていますが、一向にインフレになる気配などなく、逆にデフレ傾向が酷くなる一方です。まさに国が借金をいくらしても、インフレにはならないという事例を日本が実例として世界に示しているわけです。かように日本の例をみて、どの国もいくら借金しても大丈夫というような雰囲気が拡大していく可能性も高く、それがMMTという金融理論として経済理論化されたことも大きいわけです。
一方で、現実的にはこのMMT理論は米経済界の主流派からは徹底的に叩かれています。FRBのパウエル議長は「自国通貨での借り入れが可能な国にとって赤字は問題でないという人もいるが、私は間違っていると思う」とMMT理論をはっきりと否定しています。しかしながらわざわざFRB議長が発言することで、このMMT理論が話題となり世界に広まってきたのは皮肉です。
さらにハーバード大学の経済学長のサマーズ元米財務長官は、「MMTは非主流派エコノミストの馬鹿げた主張である」と切って捨て「MMTのアプローチは一定の地点を越えれば超インフレになる可能性があり、通貨崩壊のリスクがある」と激しく非難しています。
さらに峻烈なのは世界最大の資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンクCEOです。「MMTはクズ!」と一蹴して「財政赤字は非常に重要な問題と確信している。財政赤字は金利をずっと高く、持続不可能な水準に押し上げる可能性があると私は信じている」とMMTは問題外として逆に米国の財政赤字拡大傾向に警鐘を鳴らしています。
かように米国の経済界の主流派はMMT理論に対して激しく反発しています。ただ通常であれば話題にもならなかったようなMMTのような理論が今や、公然と議論されるようになり、政治家や一部の国の政権において極めて好意的に受け入れられてきたこと自体が重大な変化です。
| 19/12 | |
| 19/11 | |
| 19/10 | |
| 19/09 | |
| 19/08 | |
| 19/07 | |
| 19/06 | |
| 19/05 | |
| 19/04 | |
| 19/03 | |
| 19/02 | |
| 19/01 |
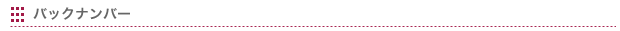
| 25/12 | |
| 25/11 | |
| 25/10 | |
| 25/09 | |
| 25/08 | |
| 25/07 | |
| 25/06 | |
| 25/05 | |
| 25/04 | |
| 25/03 | |
| 25/02 | |
| 25/01 | |
| 24/12 | |
| 24/11 | |
| 24/10 | |
| 24/09 | |
| 24/08 | |
| 24/07 | |
| 24/06 | |
| 24/05 | |
| 24/04 | |
| 24/03 | |
| 24/02 | |
| 24/01 | |
| 過去年 | |


★『大恐慌入門』
(2008年12月、徳間書店刊)に引き続き、『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)が2009年5月に発売。その後 家族で読めるファミリーブックシリーズ『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)が同年5月30日に発売。さらに2009年11月には、船井幸雄と朝倉氏の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)が発売され、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を、2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を発売、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
を発売、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/
 経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』
経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』(2008年12月、徳間書店刊)がアマゾンランキング第4位を記録し、2009年5月には新刊『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)および『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)を発売。2009年11月に舩井幸雄との初の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を発売。2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/