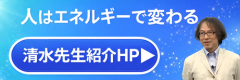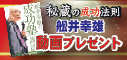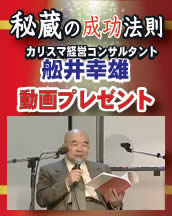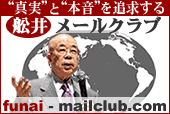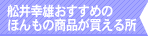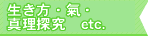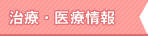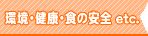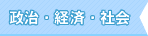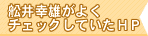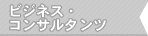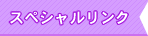“超プロ”K氏の金融講座
このページは、舩井幸雄が当サイトの『舩井幸雄のいま知らせたいこと』ページや自著で、立て続けに紹介していた経済アナリスト・K氏こと
朝倉 慶氏によるコラムページです。朝倉氏の著書はベストセラーにもなっています。
「スタッフ大募集、時給1813円」
昨年暮れの繁華街では居酒屋中心に人手不足が顕在化、何と募集広告に居酒屋のアルバイトで時給1800円を越えるケースが出てきたと話題になりました。
今年に入って再びコロナ感染が激増しているためについ1ヵ月前の状況は遥か昔の好況下の時にように感じますが、かようなアルバイトの時給が1800円を越える時代になってきたことに驚かされたのです。
実際問題、コロナ禍ではやっと顧客が戻ってきたと思っていたら再び緊急事態宣言が発令されるなど、飲食業は惨憺たる状況に追い込まれています。それでもつい1 ヵ月前にかような時給の大暴騰が起こったことは頭に入れておく必要があります。
●「時給1800円」という高額なバイト代は何を意味するのか?
株の世界などではいきなり個別の株が大暴騰し始めるケースがあるのですが、そのような場合、総じてその会社を巡る情勢が激変しているケースがほとんどです。
「大暴騰するということは何か」と言うと、会社を取り巻く環境が劇的に変わって、その会社の変化を先取りする形で株価の激変が生じるわけです。この昨年暮れの時給1800円の話は各所で話題になったのですが、一般的には突如起こった極端な人手不足がもたらした異常なバイト代の上昇と捉えられています。
そういう意味では日本の賃金全体の上昇傾向は極めて低いので、かようなバイト代の高騰は続くわけもないと思われています。また日本政府も日本全体の景気浮揚のために、各企業に積極的な賃上げを要求するなど、給料の上がらない日本の賃金体系も問題にされ続けています。かように依然、日本全体としてみると、日本の賃金体系が一朝一夕に変われて、賃金全体が恒常的な上昇傾向になるとは思えないのです。
しかしながら私は、昨年暮れのバイト代の大暴騰は今後の日本全体の恒常的な「賃金上昇の流れが始まる重要な分岐点」が訪れたシグナルと感じます。
長年賃金が上がらず、経済成長も低迷し続けた日本ですが、何か画期的な変化が生じつつあるように感じます。
振り返ってみて、なぜ時給1800円などという途方もないバイト代が生じたのか? ということです。
これは単純に、ここまでバイト代を上げないと人が集められなかったからです。ところが昨年暮れの状況を思い出してください。
確かにコロナ禍で苦しむ現在とは違って、昨年暮れはコロナ感染が下火になって人々が繁華街に積極的に出てくるようになりました。それでも昨年暮れの段階では依然、病み上がりのようなところがあり、企業はじめとして忘年会などは自粛されていたわけです。いわば、昨年暮れの段階ではコロナ感染が拡大する以前の状態と比べればお酒を飲みに行く人とか、お酒で宴会をする機会などコロナ前と比較して格段に少なかったはずです。そういう意味では幾分経済活動が回復してきたとはいえ、それほど激しい人手不足が起こるような状態でなかったはずです。
ちなみに、雇用の全体的な状況を測る日本の有効求人倍率は、昨年暮れは1.15と高い水準ではありません。この有効求人倍率は2018年は1.62まで上昇していたのです。
その後、コロナの拡大もあり、求人数は激減、日本経済は失速していました。ですから立ち直りきれない昨年末の段階では、日本全体それほど高い有効求人倍率ではなかったのです。であれば、バイトする人もある程度は確保できたと思うのですが、全く人が集まらずにバイト代が暴騰となったわけです。
ちなみにパート、アルバイトの平均時給の推移を過去15年間の統計を遡ってみますと、2007年4月の段階では928円でした。それがじわじわ上げてきたものの、2014年の段階でも950円程度だったのです。いわばこの2007年から2014年まではパートやアルバイトの時給はほんの少しずつ上がっただけでした。時給の1000円割れが続いて、当時は最低ラインとして時給1000円を支払うべきというような議論もありました。
またこのコラムを読んでいる多くの人も、パートやアルバイトの時給は1000円程度との認識を持っている人が多いのではないでしょうか。ところがこのパートとアルバイトの時給は、2015年くらいから恒常的に上がり始めます。各年の暮れ12月の時給の推移をみると、2016年1006円、2017年1030円、2018年1058円、2019年1089円、2020年1100円、2021年は1103円となりました。これは日本全国の平均となりますが、みたように毎年上がり続けています。
特にコロナ禍におけるここ2年も全く下がらず、上がり続けたことは注目です。
通常、パートやアルバイトの時給は、まさに需要と供給の関係でキッチリ決まってきます。正社員の賃金となりますと、下げることができないとか、雇用を守る必要があるとか、政治的な要請も働きますので、大きく変わるには時間もかかります。しかしながらそのような様々なしがらみもなく需給だけの関係で上げたり下げたりできるのがパートやアルバイトの時給です。
そのパートやアルバイトの時給はかように一直線で上がり続けているのです。しかも東京という日本の中心地ではありますが、いきなり1800円という異常値が出現しました。こうみていくと上がらない日本の賃金も、上がってきたパートやアルバイトの時給のように上がり始める時が迫ってきたように思えるのです。
●賃金上昇の裏に予想される現実
すでに日本でも転職市場は大活況となってきました。米国では人手不足が顕著で職場を変えるたびに給料が上がり、実際、賃金は昨年に比べて4.7%上昇しているとの調査結果が出てきています。一方、日本では依然正社員の賃金の大幅な上昇は起こってきていませんが、転職市場は違います。日本でも転職は以前と比べて盛んになりつつあり、いわゆる転職市場の有効求人倍率はうなぎのぼりなのです。昨年7月の統計ですと、転職求人倍率は日本全体で2.31、IT関連ですと6.82、サービス関連ですと2.74、メディカル関連が2.23、金融関連が1.59という具合です。かように多くの分野で人手不足が目立ってきていますので、日本でも転職のたびに給与が上がるというケースが相次いできたのです。
どうも日本全体は圧倒的な人手不足状態に陥ってくる寸前の状態のようです。日本の人口減は多くの人の知るところです。米国などは人口が増えていますが、日本は世界に先駆けて少子高齢化が進み、移民でも来ないと深刻な労働力不足に陥ると指摘され続けてきました。ところが日本全体としてみると、そのような具体的な痛みを感じたことはないと思います。物価も日本は諸外国と比べれば比較的に安定しています。
しかし日本はなぜ、人口が減り続けているのに極端な労働力不足に陥らなかったのでしょうか? 実はここに「団塊の世代」の活躍という隠れた実体があるのです。一般的に現役世代、働ける人は15歳から64歳までとされ、その年代の人口を生産年齢人口と言います。
日本ではこの生産年齢人口の減少が著しいこととなり、危機的な状況となっています。日本の生産年齢人口の推移をみると、1997年には8700万人となりピークとなりました。その後、日本全体の人口減を背景として生産年齢人口は減る一方で、昨年2021年の段階では7580万人となりました。生産年齢人口はわずか24年で1120万人、率にして13%減という驚くべき減少となったのです。普通、これだけの短期間でこれだけ働ける人が減ってしまっては社会が持ちませんし、労働力の不足で極端な高賃金や混乱が生じてくるはずです。ところが日本社会は不思議と安定していました。日本では生産年齢人口、15歳から64歳までに人が大きく減り続けたのに、どうして労働力の不足が生じなかったのでしょうか? 実は65 歳以上の人が働き続けたからなのです! 特にここ10年は日本で最も人口が大きい団塊の世代(1947年から1949年に生まれた世代)が70代に達する手前の時期であり、この世代が現役を引退しても何らかの形で仕事をやり続けていた関係で、幸運なことに日本では極端な労働力不足が起こらなかったのです。
また、日本では同じく女性の労働参加も拡大した関係で、これも労働力不足を補いました。驚くべきことですが、過去24年、これだけ生産年齢人口が減少している間、日本では労働力人口の減少が起きなかったのです。まさに団塊世代をはじめとする最も人口が多い層が現役引退後も活躍し続けたわけです。このあたりに高齢化でも働くことができる時代の変化を感じます。
ところが今、直近で起こってきたことは何かと言いますと、いよいよこの人口の最も多い世代、団塊の世代はついに70歳を超え、間もなく75歳に近づいていきます。何歳まで働くことができるかという統計とみると、70歳までは働ける人が多いのですが、70歳を過ぎると働けなくなる人が激増するのです。そしてついに日本において70歳を過ぎた団塊の世代の労働市場からの撤退が加速化してきたわけです。こうなると日本は本当に労働力不足となっていくのです。
昨年の時給1800円の出現は、かような日本における「本格的な深刻な労働力不足の時代」が渡来しつつあることを示している可能性が高いのです。日本各所で深刻な人手不足となれば、どこでも賃金を上げなければ人を確保することなどできなくなります。そうなればその結果として、需要と供給の関係から日本の賃金全体の本格的な上昇が始まってきておかしくないと思うのです。
経済学では賃金が本格的に上昇する典型的な局面があり、それを「ルイスの転換点」と呼んでいます。
「ルイスの転換点」とは何か? これはどの国においても起こってきた典型的な賃金上昇局面の到来なのですが、例えば日本ですと1960年代、終戦後しばらくして日本は高度成長時代に入り年率10%を超える二桁成長を続ける時代となりました。当時、依然日本の地方に多くの若者が農業に従事していたわけですが、これら若者は職を求めて東京など大都市にやってきます。いわゆる地方から東京への集団就職時代の始まりでした。当時の東京、上野駅などは連日集団就職のために上京する人でごった返していたわけです。かような情勢ですと農村や地方からいくらでも職を求めて上京する人が絶えない状況ですから、それを受け入れる企業側としても次々と訪れる集団就職の労働者について、さほど給与を引き上げる必要もなかったわけです。
ところが農村部や地方からほとんどの若者などが上京して出ていくと、いよいよ地方は人が少なくなり、東京など大都市に上京する人が激減してくるわけです。かように豊富だった農村部からの労働力の供給が減ってくる時点、いわば労働力不足が生じてくる時点を捉えて「ルイスの転換点」というわけです。この「ルイスの転換点」を通過すると労働力不足が顕在化してきますので、この時点から恒常的な賃金上昇が始まってくるわけです。
中国などでも同じで、2000年まではいくらでも農村から労働者がやってきて尽きない人が押し寄せてきた関係で、企業は安く人を雇うことができたのです。ところが2000年を過ぎて、中国においても農村部からの労働力供給が抑えられるようになると、これはいわゆる「ルイスの転換点」となって賃金の恒常的な上昇が始まってきたわけです。かようにどの国においても「ルイスの転換点」を経て労働力不足から賃金上昇が始まってくるわけです。
そして注目は現在の日本です。これはいわゆる「第2のルイスの転換点」が生じつつあるとみていいでしょう。ここまで見てきたように、日本では生産年齢人口が急激に減少してきたのですが、それを主に団塊の世代をはじめとする人口の最も大きかった層が労働力となって定年後も日本の労働市場を支えてきたわけです。これが本当は危機的になるはずだった日本の労働市場を救ってきました。ところがついに団塊の世代は75歳に近づき、労働できなくなり、真のリタイアとなってきたわけです。この労働力減少いう水面下で起こりつつあった変化は、コロナ禍という極端な突発的な不況で見えなかったのですが、昨年末、少しだけ好況に転じた時点で見えてきて、いきなり時給1800円という極端なことが起こったわけです。となると、これからの日本の労働力の不足は本当に深刻化してくる可能性が高いと思います。賃金は上がってくるでしょうが、それは日本全体の極端な労働力不足を写したものであり、日本全体の経済の活況を示唆するものではありません。
現役世代は、引退した高齢者を直接的にも間接的にも支えなければならないわけです。今後、日本では増税かインフレ到来か、その両方か、何が起こるかわかりませんが、現役世代の給料は上がっていくでしょうが、負担は拡大し続ける未来が待っています。やっと給料が上がる世界が訪れるのですが、それが手放しのハッピーとはいかないわけです。
| 22/12 | |
| 22/11 | |
| 22/10 | |
| 22/09 | |
| 22/08 | |
| 22/07 | |
| 22/06 | |
| 22/05 | |
| 22/04 | |
| 22/03 | |
| 22/02 | |
| 22/01 |
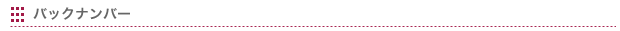
| 26/02 | |
| 26/01 | |
| 25/12 | |
| 25/11 | |
| 25/10 | |
| 25/09 | |
| 25/08 | |
| 25/07 | |
| 25/06 | |
| 25/05 | |
| 25/04 | |
| 25/03 | |
| 25/02 | |
| 25/01 | |
| 過去年 | |


★『大恐慌入門』
(2008年12月、徳間書店刊)に引き続き、『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)が2009年5月に発売。その後 家族で読めるファミリーブックシリーズ『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)が同年5月30日に発売。さらに2009年11月には、船井幸雄と朝倉氏の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)が発売され、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を、2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を発売、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
を発売、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/
 経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』
経済アナリスト。
株式会社アセットマネジメントあさくら 代表取締役。 舩井幸雄が「経済予測の“超プロ”」と紹介し、その鋭い見解に注目が集まっている。早い時期から、今後の世界経済に危機感を抱き、その見解を舩井幸雄にレポートで送り続けてきた。
実際、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに、その経済予測は当たり続けている。
著書『大恐慌入門』(2008年12月、徳間書店刊)がアマゾンランキング第4位を記録し、2009年5月には新刊『恐慌第2幕』
(ゴマブックス刊)および『日本人を直撃する大恐慌』
(飛鳥新社刊)を発売。2009年11月に舩井幸雄との初の共著『すでに世界は恐慌に突入した』
(ビジネス社刊)、2010年2月『裏読み日本経済』
(徳間書店刊)、2010年11月に『2011年 本当の危機が始まる!』
(ダイヤモンド社)を、2011年7月に『2012年、日本経済は大崩壊する!』
(幻冬舎)を発売。2011年12月に『もうこれは世界大恐慌』
(徳間書店)を、2012年6月に『2013年、株式投資に答えがある』
(ビジネス社)を、2012年10月に朝倉慶さん監修、ピーター・シフ著の『アメリカが暴発する! 大恐慌か超インフレだ』
(ビジネス社)を発売。2013年2月に『株バブル勃発、円は大暴落』
(幻冬舎)を、2013年9月に『2014年 インフレに向かう世界 だから株にマネーが殺到する!』
(徳間書店)を 、2014年7月に『株は再び急騰、国債は暴落へ』
(幻冬舎)を、2014年11月に舩井勝仁との共著『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』
(ビジネス社)を発売、2015年5月に『株、株、株!もう買うしかない』
、2016年3月に『世界経済のトレンドが変わった!』
(幻冬舎刊)を発売、最新刊に『暴走する日銀相場』
(2016年10月 徳間書店刊)がある。
★朝倉慶 公式HP: http://asakurakei.com/
★(株)ASK1: http://www.ask1-jp.com/